「うまく対応できなかったらどうしよう…」
患者さんやご家族との関わりに、不安や戸惑いを感じたことはありませんか?
理学療法士として働く中で、技術や知識だけでなく「人との関わり」が求められる場面は多くあります。
ときには言葉の行き違いやクレーム、理不尽な対応で、心がすり減るような思いをすることもあります。
本記事では、私自身の経験も交えながら、患者対応における「しんどさ」の正体と、心が疲れきる前にできる工夫について解説します。
同じように悩む方にとって、少しでも気持ちが軽くなるきっかけになれば幸いです。
よくある「しんどさ」の理由
1. 言葉の一つひとつを気にしすぎてしまう
患者さんに対して「失礼がないように」「誤解されないように」と慎重に言葉を選びすぎて、かえって緊張してしまうことがあります。
特に新人や経験が浅いうちは、些細な一言でも「まずかったかな」「嫌な思いをさせたかも」と気になってしまい、必要以上に疲れてしまうことも。
相手の反応を深読みしすぎることで、自分自身の言動に自信をなくしてしまうことがあります。
2. クレームや否定的な言葉への恐怖
患者さんやご家族からの何気ない一言に、心が大きく揺れることがあります。
たとえば、「あの先生は冷たい」といった評価を耳にすると、どんなに丁寧に対応していても自己否定に陥ることがあります。
また、上司や先輩からの指摘も「揚げ足を取られている」と感じてしまうことがありました。
私自身も、患者対応で迷ったことを相談した際、「そんな対応はおかしい」と強く言われ、患者さんとの関わり自体が怖くなった経験があります。
3. 自分の対応に自信が持てない
経験が浅いほど「これで合っているのか?」という不安がつきまといます。
特に精神的な疾患や高齢の患者さんなど、対応に気を遣う場面では、「何を言えばいいかわからない」と立ち止まってしまうことも。
周囲にすぐ相談できる環境があればいいのですが、忙しい職場では孤独感を感じやすく、対応に迷ったまま自己嫌悪に陥ることもあります。
心が疲れきる前にできる3つの工夫
1. 自分の中で“線引き”をする
すべての人に好かれる必要はありません。
感じ方や受け取り方は相手次第で、自分の言動すべてが思い通りに伝わるとは限らないと理解することで、心が少し軽くなります。
「相手の問題」と「自分の課題」を分けて考えるクセをつけることで、不必要に自分を責めることが減ります。
2. 記録を見返して“事実”を確認する
対応に迷ったとき、後から記録を見返すことで「自分はしっかりやっていた」と思えることがあります。
私も、クレームを受けた際に記録を確認し、「説明も丁寧にしていた」と再認識できて、少し気が楽になった経験があります。
感情ではなく、行動や言葉の“事実”に目を向けることで、不安や後悔を整理しやすくなります。
3. 周囲と「振り返る場」をつくる
1人で抱え込まず、チームや先輩と「対応についてどう感じたか」を共有できる機会があると、安心感につながります。
新人の頃、先輩と一緒にケースを振り返る時間があり、「あの場面で迷ったのは当然だよ」と言ってもらえたことで救われたことがあります。
心理的安全性のある職場環境は、患者対応のしんどさを減らす大きな要素です。
しんどさを感じたあなたへ
患者さんとの関わりで「もう無理かも…」と感じることがあっても、それはあなたが一生懸命向き合っている証拠です。
無理にポジティブになる必要はありませんが、「少し距離を置いてみる」「先輩に頼ってみる」など、心を守る行動をとることはとても大切です。
日々、患者さんに寄り添うあなた自身にも、優しさと余白が必要です。
どうか、自分を責めすぎず、しんどさに気づけた自分をまずは肯定してください。
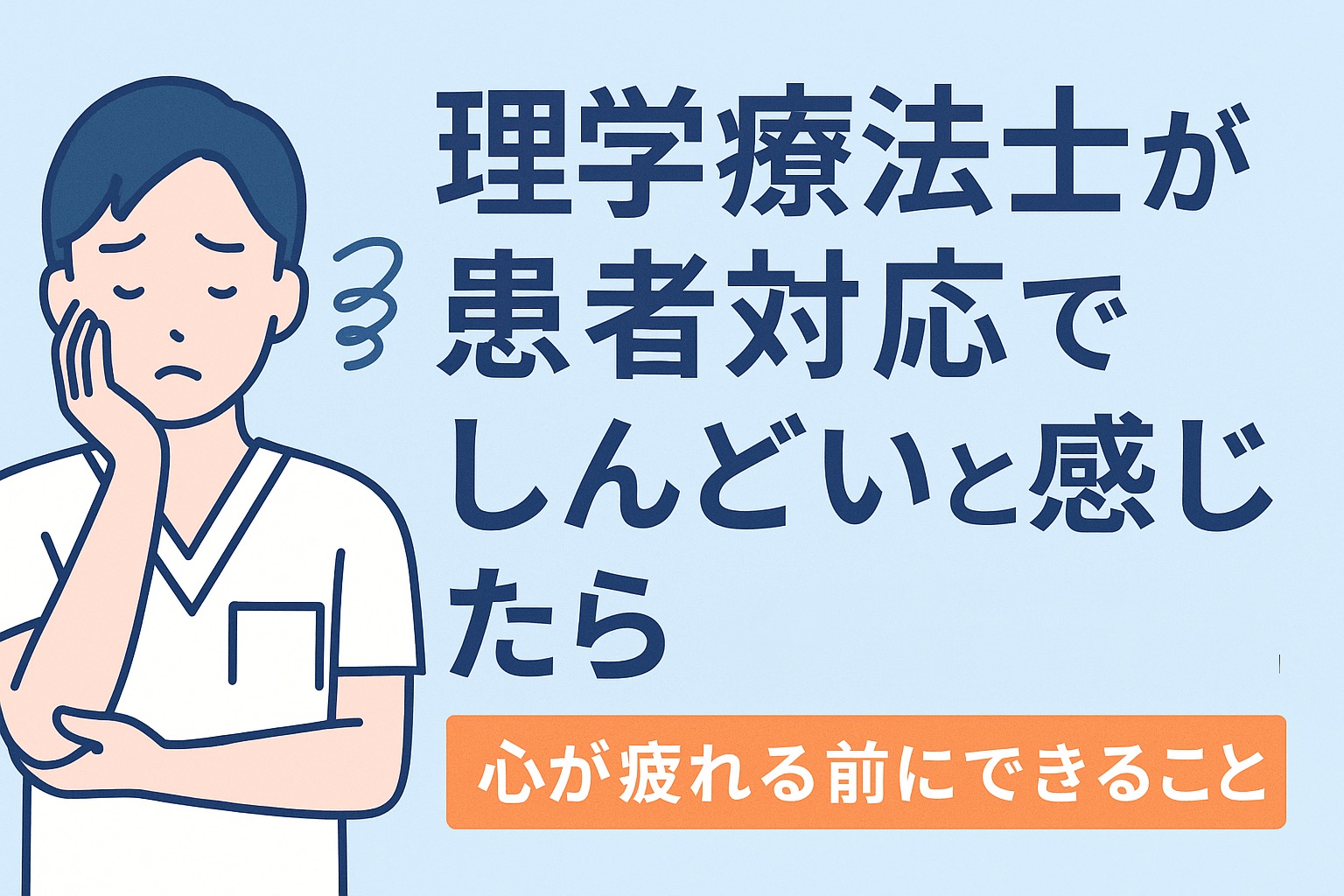
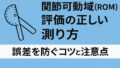
コメント