「関節可動域(ROM)って、ちゃんと測れてるかな…」
そんな不安を感じたことはありませんか?
理学療法士として働き始めて間もない頃、ROM評価は“基礎中の基礎”だからこそ、正しく測れているのか不安になることがあります。
私自身も、新人時代に上司と数値が合わず、何度も測り直した経験がありました。
この記事では、そんな新人〜若手セラピストの方に向けて、ROM評価の精度を高めるための基本と、現場ですぐ使えるポイントを紹介します。
どうしてROM評価の精度が大事なの?
ROMの数値は、患者さんの機能評価、治療効果の判定、そして記録の根拠にもなります。
「なんとなくこのくらいで…」という感覚で測ってしまうと、前回と違う結果になったり、先輩やDrと話が合わなくなったりしてしまいます。
評価がしっかりできると、自信にもつながりますし、患者さんやチームからの信頼も自然とついてきます。
誤差が起きやすいポイントはここ!
- 測定姿勢がバラバラ
例:仰臥位で測るつもりが、いつの間にか座位で測っていた…なんてことありませんか? - 代償動作を見逃してしまう
骨盤や体幹が動いても気づかず、正確な関節の動きが測れなくなります。 - ゴニオメーターの軸がずれる
ランドマークがわからないまま測っていると、数値の再現性が低くなります。 - 終末感の判断が曖昧
自分が「ここまでかな?」と感じたところが、他の人とは違っていた…ということもよくあります。
測定誤差を防ぐための5つのポイント
1. 姿勢と測定条件を統一しよう
毎回同じ体位・同じ関節角度で測ることが大前提。
仰臥位・側臥位・座位など、最初に決めた測定姿勢を記録しておくのもおすすめです。
2. 代償動作をブロック!
骨盤・体幹の代償を見逃すと、実際より多く動いているように見えてしまいます。
例えば股関節屈曲では、反対側の骨盤をしっかり押さえるなど工夫しましょう。
3. ゴニオメーターは「軸合わせ」が命
基本軸・移動軸の理解が曖昧なままだと、測るたびに数値がズレます。
解剖学的ランドマークを毎回しっかり確認するクセをつけましょう。
4. 終末感の判断を「共有」しよう
「どこをROMの終わりとするか?」を、先輩と話してみたことはありますか?
痛み? 抵抗? 他動の限界? 自分の中で基準を持ち、同僚とも共有できると◎です。
5. 先輩や同期と“フィードバック”をもらう
評価が合っているか自信がないときは、素直に確認するのが成長の近道。
「もう少しこっちが固定されてるといいね」など、ちょっとしたアドバイスが精度アップに直結します。
便利ツールの活用もアリ!
最近は、スマホアプリや電子ゴニオメーターを使ってROMを測る方法も増えています。
もちろん、基礎的な測定スキルがあってこそですが、補助的に使うことで客観性を高めることができます。
最後に
ROM評価は、理学療法士の基礎スキルの中でも、意外と奥が深い領域です。
「なんとなく測る」から一歩抜け出し、根拠のある評価ができるようになると、臨床の幅もぐんと広がります。
今日からできることから一つずつ。
自信を持って評価できるよう、ぜひ現場で試してみてください。
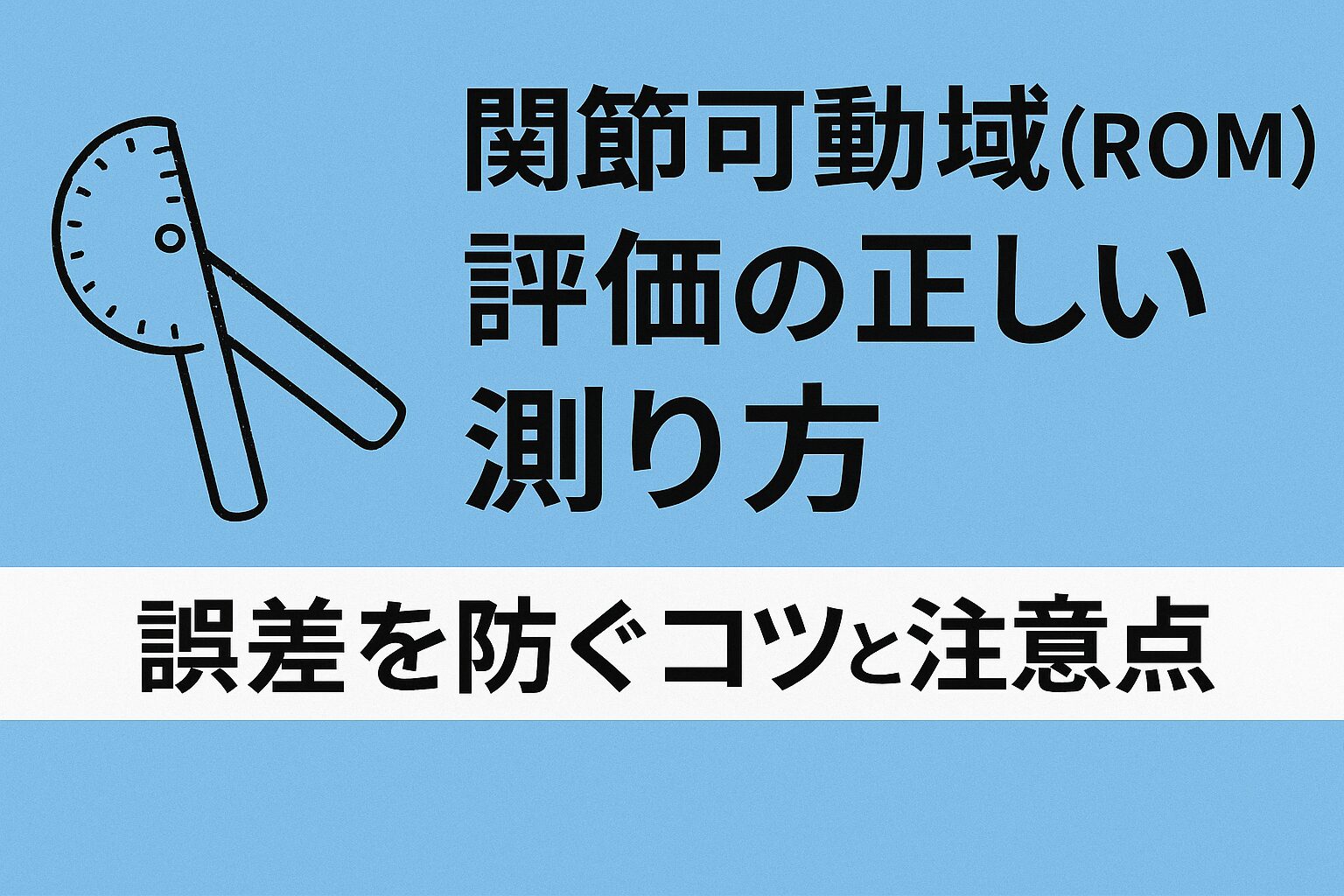

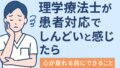
コメント