はじめに
「歩行速度は“第6のバイタルサイン”である」と言われるほど、臨床では歩行能力の評価が重視されています。
中でも10メートル歩行テストは、理学療法士が現場で最も多く使う基本的かつ重要な評価指標のひとつです。
シンプルな検査でありながら、測定方法や解釈に違いが出やすいため、正しく理解しておくことが臨床力の差につながります。
この記事では、10メートル歩行テストの基本から、臨床での活かし方までを徹底解説します。
10メートル歩行テストとは?
10メートル歩行テスト(10mWT)は、被験者が歩行に要する時間から歩行速度(m/s)を算出する評価法です。
主な目的
- 歩行能力の定量的評価
- 回復状況のモニタリング
- ADLレベル・在宅復帰の予測
よく使われる測定条件
- 通常歩行(comfortable gait speed)
- 最大歩行(fast gait speed)
- 補助具の有無・介助レベルも記録が必要
正しい評価方法と測定手順
測定手順を統一することで、信頼性の高いデータが得られます。
基本の流れ
- 評価環境を整える:床面は平坦で安全な環境。靴・杖などの条件は再現性をもって行う。
- 測定ラインを設定する:合計14メートルの直線コースを確保 →「前後2mの助走・減速区間+中央10mの計測区間」
- タイミングの取り方:助走区間に入った時から歩き始め、10mラインを通過するタイミングでストップウォッチを開始/停止
- 歩行速度の計算:歩行時間(秒)÷10(m)= ○○ m/s
結果の見方と臨床での活かし方
歩行速度のカットオフ値(参考)
| 歩行速度 | 意味・解釈 |
|---|---|
| < 0.4 m/s | 屋内生活が中心。移動に支援が必要なレベル |
| 0.4〜0.8 m/s | 屋外歩行に制限あり。要介護高齢者の目安 |
| > 0.8 m/s | 自立した屋外生活が可能。在宅復帰が現実的 |
| > 1.0 m/s | 高齢者の平均。健康的な生活水準を示す |
臨床での活用ポイント
- 在宅復帰の判断材料:「0.8m/s以上」が目安
- 介護サービス調整時の根拠:訪問リハや通所リハの選択など
- 経時的変化の把握:週1回の測定で回復傾向を確認
- 歩行補助具・装具選定:定量的な根拠として活用可能
注意すべき測定ミスと改善策
10メートル歩行テストはシンプルな分、測定ミスも起こりやすいため注意が必要です。
よくあるミス
- 開始/終了のタイミングのズレ(前後2mの助走・減速を含めてしまう)
- ストップウォッチの押しミス
- 利用者が“見られている”意識で意図的に速く歩いてしまう
対策
- できるだけ同じ評価者が測定
- 訓練されたスタッフがタイミングを取る
- 通常歩行のテストをする場合、利用者には「いつものペースで」と説明する
他の歩行評価との使い分け
10メートル歩行テストだけで全てを判断するのではなく、他の歩行関連評価と目的に応じて組み合わせることで、より多角的な判断が可能になります。
| 評価法 | 特徴・違い |
|---|---|
| TUG(Timed Up and Go) | 起立〜歩行〜方向転換〜着座を含む。ADL・転倒予測に有用 |
| 6分間歩行テスト(6MWT) | 持久性・全身的運動耐容能の評価。COPDや心疾患などに多用 |
| 10mWT | 歩行速度に特化した簡便な指標。定量的比較に優れる |
まとめ
10メートル歩行テストは、理学療法士にとって非常に基本的かつ重要な評価ツールです。
- 歩行速度は「在宅復帰」や「QOL予測」に直結する指標
- 測定手順を正しく守ることで、臨床判断の精度が上がる
- 他の評価と組み合わせて、より信頼性のある判断材料に
評価そのものを「作業」で終わらせず、「意味のある数値」として活用できるよう、ぜひ見直してみてください。
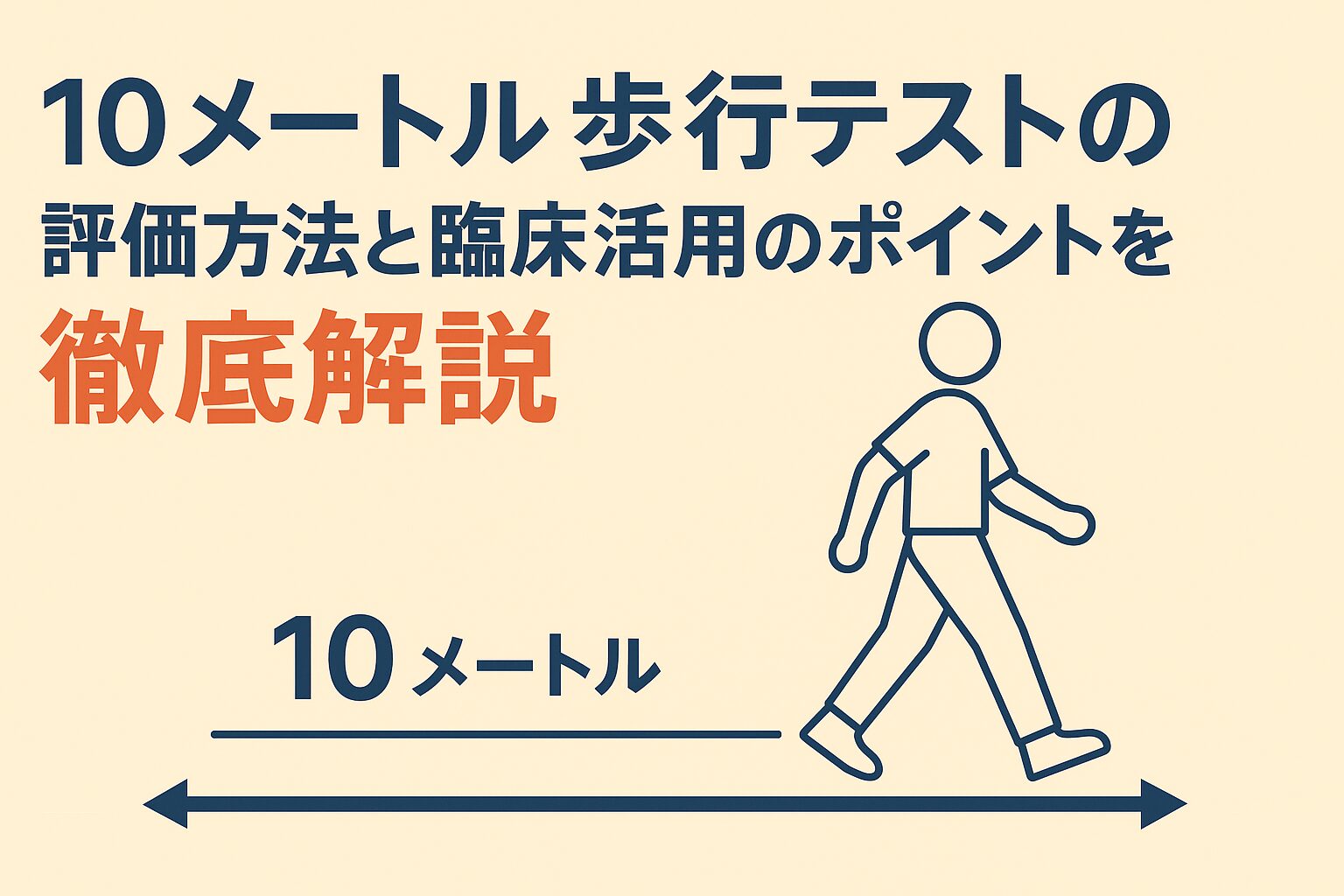


コメント