はじめに
6分間歩行テスト(6MWT)は、心肺持久力やADL能力を簡便に評価できるテストとして、多くの臨床現場で使われています。
しかし「方法があいまい」「本来の目的が不明確なまま実施されている」と感じたことはないでしょうか?
この記事では、6MWTの基礎から臨床活用、カットオフ値、見落としやすいポイントまで、理学療法士が知っておくべき実践的な知識を1本にまとめました。
あわせて読みたい関連記事:
6分間歩行テスト(6MWT)とは?
6MWTは、患者が6分間に歩ける最大距離を測定する検査です。
心肺機能、歩行能力、リハビリ効果の把握に用いられ、特別な機器が不要なため、急性期から在宅リハまで幅広く実施されています。
目的と評価の意義
- 心肺持久力の簡便な評価(心疾患・呼吸器疾患)
- 歩行能力やADLの定量的評価
- リハビリ介入効果の可視化(入院前後・退院前後)
- 他職種との情報共有や退院判断の材料として活用
屋内外移動の可否判断では、10m歩行テストの速度や、起立動作の自立度を測る5STSを併せて評価すると、退院後生活の見立てが立てやすくなります。
10m歩行テスト:測定方法と臨床での活用
5回立ち上がりテスト(5STS):評価手順と臨床応用
測定方法と環境設定
✅ 一般的な測定方法は「直線20~30mの往復方式」
ガイドライン(ATS 2002)に基づいた標準的な方法では、直線の廊下を往復して距離を測定します。
方向転換が含まれており、日常生活に近い歩行負荷が再現されやすい点が特徴です。
✅ 周回方式(50mリハ室の周回)でもOK?
施設の構造やスペースに応じて「周回方式」も実施可能です。ただし、以下の点に注意しましょう:
- 曲がり角が少なく、距離がやや伸びやすくなる傾向
- 他施設との比較には「コース形状」を明記しておく
- 同じ患者においては、同じ方式・コースで評価することが重要
➡ どちらの方式でもよいですが、再現性と記録の統一が必要です。
測定の基本手順
- コースの設定(直線20〜30m または周回方式)
- 安静時のバイタル測定(SpO₂・HR・BP)
- 患者へ説明:「6分間でできるだけ長く歩いてください」
- タイマー開始(必要最低限の声かけにとどめる)
- 6分経過後に終了を伝え、歩行を停止
- その場で再度バイタルを測定、歩行距離・補助具の有無・主観的疲労度(Borgスケール)などを記録
カットオフ値・臨床的基準(疾患別・機能別・効果判定)
6MWTで得られる距離(6MWD)は、疾患の重症度や予後、治療効果の評価に活用されます。
以下は信頼性の高い臨床研究や報告をもとに整理した代表的なカットオフ値です。
◼︎ 心不全:約300m未満
- 予後不良、再入院や死亡リスクが高いとされる
- 300mを境に生命予後の分岐点として使われることが多い
◼︎ COPD:約317~350m未満
- 死亡率が高くなる傾向が報告されている
- 呼吸リハビリ導入の重要な判定基準
◼︎ 肺高血圧症:440m以下(中リスク)、165m未満(高リスク)
- 440m以上:低リスク
- 165m未満:高リスク
◼︎ 回復期リハビリ:200m以上
- 屋外歩行が可能とされる目安:205m以上
- 地域移動に制限のない目安:288m以上
◼︎ 高齢者:約400m以上
- フレイルやサルコペニアの評価で400m未満が指標
- 転倒リスクの判断にも用いられる
◼︎ 自立歩行・屋外移動の可否:213m
- 213m以上歩行可能なら自立した屋外移動が見込まれる
◼︎ 治療効果の判定(最小有意差)
- 心不全:+45m以上の改善で治療効果あり
- COPD:+70m以上の改善で有意な変化
見落とされやすいポイント
- 最大努力になっていない
「できる限り長く歩きましょう」と明確に伝える - バイタル測定のタイミングが曖昧
安静時、終了直後、回復後のタイミングで記録する - 測定環境が不適切
距離が短すぎたり人通りが多いと再現性が損なわれる - 声かけに個人差がある
統一ルールを設け、「残り◯分です」のみなどに統一 - 数値だけで判断してしまう
体調・精神状態・疼痛など背景要因も考慮する
評価のコツと応用のヒント
- Borgスケールを併用して主観的負荷も評価
- 結果をグラフ・記録表にして視覚的に共有
- 10m歩行やTUGなどと併用して多面的に捉える
- モチベーションや疾患背景との関連にも注目
まとめ|6分間歩行テストを「使える評価」に変える
6分間歩行テストは、特別な機器を使わずに心肺・歩行能力を数値化できる、非常に優れた評価ツールです。
ただし、正しい方法と背景知識を持たなければ、本来の価値を引き出すことはできません。
重要なのは、評価前後の準備・環境整備・声かけの統一・数値の解釈。
たった6分で、臨床判断の精度と説得力を大きく高められる検査です。
理学療法士として、6MWTを「ただの距離測定」ではなく「意味ある評価」として活用していきましょう。
次に読みたい記事はこちら:
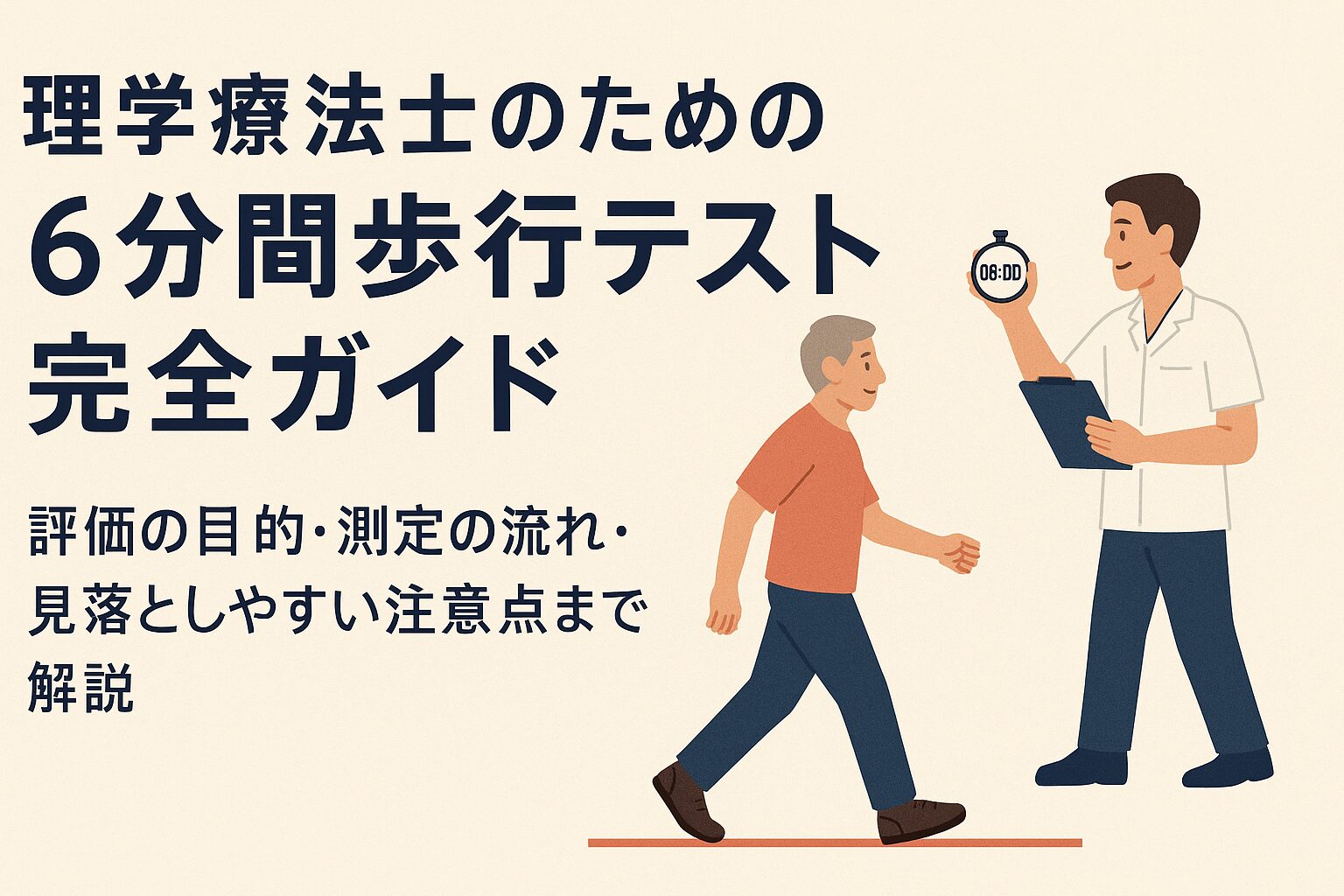


コメント