関節の可動性を改善するための徒手療法のひとつ「関節モビライゼーション」。理学療法士にとって基本的なスキルの1つですが、正しく理解し、適切に使いこなせているでしょうか?
この記事では、関節モビライゼーションの基本から臨床応用までを分かりやすく解説します。
関節モビライゼーションとは
関節モビライゼーション(Joint Mobilization)とは、関節包内運動を改善することを目的とした徒手的な治療手技です。痛みの軽減や可動域の改善、関節機能の回復を目指して行われます。
対象となるのは、関節の拘縮・可動域制限・関節包や靭帯の柔軟性低下などです。
目的と効果
- 疼痛の軽減(ゲートコントロール理論の活用)
- 関節可動域の改善
- 関節内圧の調整
- 関節包の伸張
- リラクゼーション効果
グレード分類(Maitlandの分類)
モビライゼーションは、刺激量に応じて以下のように分類されます。
- グレードI: 小さい振幅で関節可動域の始めの範囲
- グレードII: 大きい振幅で可動域の前半
- グレードIII: 大きい振幅で可動域の後半
- グレードIV: 小さい振幅で可動域の終わり
- グレードV: ハイスピード・スラスト(いわゆるマニピュレーション)
臨床では、疼痛の軽減目的でグレードI〜II、可動域改善にはグレードIII〜IVがよく使用されます。
臨床応用の例:膝関節の前方滑り
変形性膝関節症などで脛骨の前方滑りを促す場合、患者を背臥位にし、大腿部を固定しながら脛骨を前方へ滑らせます。グレードやリズムを調整し、痛みを伴わない範囲で行うことがポイントです。
禁忌と注意点
- 急性炎症期
- 骨折・脱臼直後
- 腫瘍や感染のある関節
- 重度の骨粗鬆症
対象者の状態に応じて評価・リスク管理を徹底することが重要です。
関節モビライゼーションを深く学びたい方へ
関節モビライゼーションを実際の臨床で使いこなすには、体系的な学習が欠かせません。以下の書籍は、基礎から応用まで理解できるおすすめです。私も使っています。
※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
まとめ
関節モビライゼーションは、理学療法士が基本として身につけておくべき技術です。正しい評価とリスク管理のもとで適切に実施すれば、疼痛の軽減や関節機能の改善に大きな効果が期待できます。
基礎を理解した上で、症例に応じた応用力を身につけていきましょう。
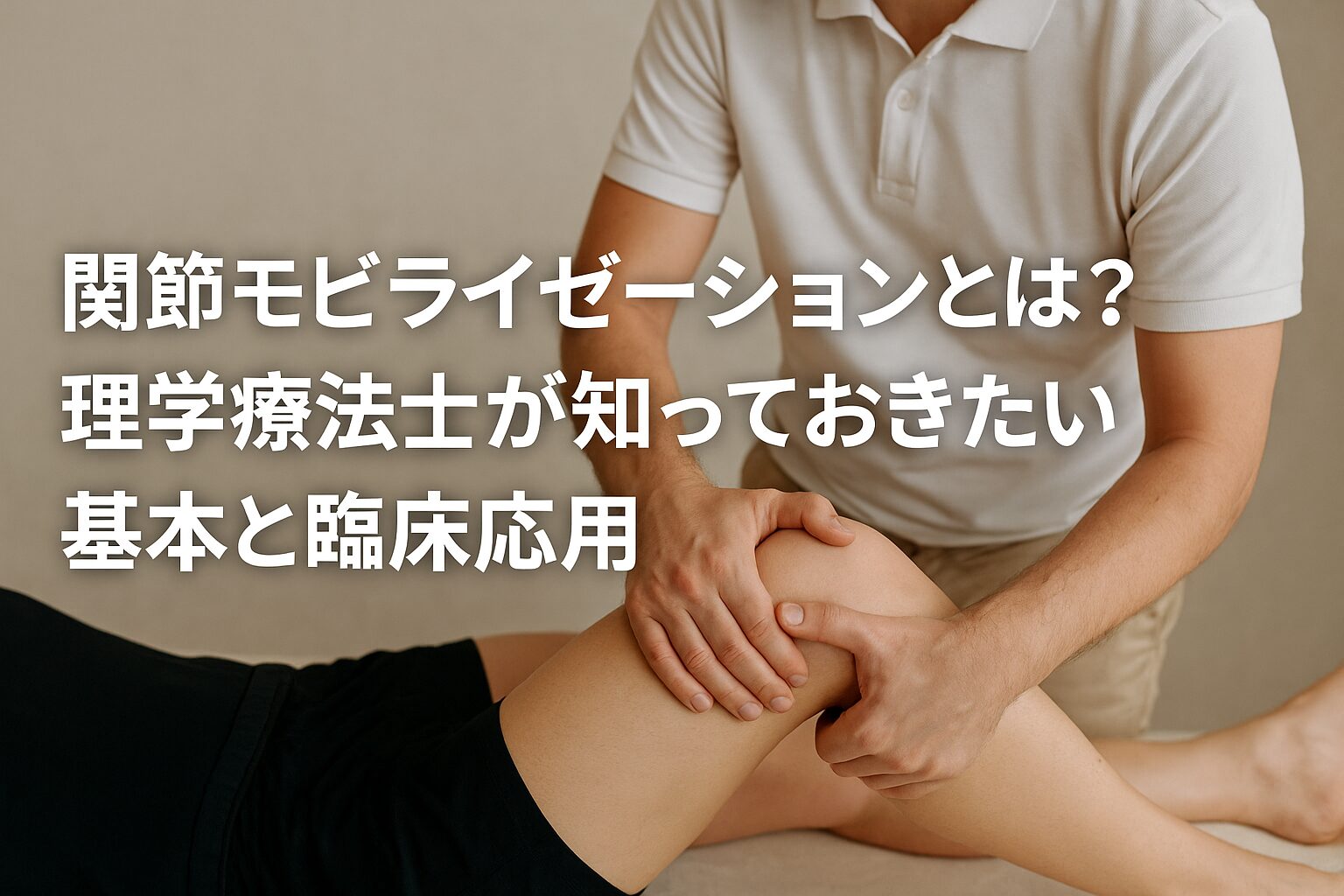


コメント