はじめに
10m歩行テストは、日常的に活用されるシンプルな評価方法ですが、歩行速度を定量的に把握することで、患者のADL予測やリハビリの方向性を明確にする大切な手がかりとなります。
特に回復期リハビリや外来リハでは、歩行能力の改善が生活の質(QOL)に直結することも多く、10m歩行テストの結果をどう読み解き、どう活かすかは臨床力が問われる部分です。
この記事では、歩行速度と歩行率が示す意味、そして評価結果を基にした課題設定のポイントを、現場視点で解説します。
10m歩行テストとは?
10m歩行テストは、平地を10メートル歩く時間を測定し、歩行速度(m/s)を算出するテストです。通常歩行(普段通りの速さ)と最大歩行(できるだけ速く)の2種類を測定することが一般的です。
測定時は、加速・減速区間として前後に2メートルずつ設けることが推奨され、計14mのスペースを確保します。10m間をストップウォッチで計測し、「10 ÷ 測定時間(秒)」で速度を算出します。
歩行速度と歩行率の違いとは?
歩行速度(m/s)
1秒間に何メートル進むかを示す数値で、移動能力の総合的な指標です。
歩行速度 = 歩幅 × 歩行率(cadence)
歩行率(歩行頻度・cadence)
1分間あたりの歩数(歩/分)を指します。通常は左右の一歩ずつを1歩とカウントします。
- 成人健常者:110〜130歩/分
- 高齢者や脳卒中患者では70〜100歩/分が多い
つまり、歩行速度が遅い=歩幅が小さい or 歩行率が低いのいずれか(または両方)ということになります。
歩行速度が示すものとは?
歩行速度は、単なる移動能力の指標にとどまらず、ADLや社会参加レベルとも強く関連しています。
- 0.4m/s以下:屋内移動が中心で、介助が必要なことが多い
- 0.6m/s以上:日常生活においてある程度自立可能
- 0.8m/s以上:地域社会での自立した生活が可能な目安
- 1.0m/s以上:信号機の青信号で安全に横断できる基準
疾患別にも指標は異なりますが、高齢者・脳卒中・大腿骨骨折などの対象では、0.8m/sが一つの「地域自立」のラインとして使われています。
歩行率が示す臨床的意義
歩行率は、特に運動リズムや神経系の機能を評価するうえで有効です。
- 歩行率が著しく低い場合、リズムの崩れや認知・注意障害を伴うことがある
- 失調性歩行やパーキンソン症状では、歩行率の急な変化やバラツキが見られる
- 歩行速度が向上しても、歩行率が過剰に高いとエネルギー効率が悪く、疲労しやすい
たとえば、同じ速度でも「歩幅が広く歩行率が低い」方が、余裕のある歩行と評価できます。
歩行速度・歩行率から予測できるADLレベル
両者の組み合わせから、以下のような日常生活への予測が可能です:
- 歩行速度が0.4m/s未満、歩行率も80歩/分以下:屋内生活でも転倒リスクや介助が必要
- 歩行速度0.8m/s前後、歩行率100歩/分前後:地域生活や買い物、通院の可能性が高い
- 歩行速度1.0m/s以上、歩行率120歩/分以上:信号の横断、公共交通の利用、自立通勤も現実的
また、歩行率の安定性や左右差を見れば、リズム感や神経系の課題も見えてきます。
歩行速度と歩行率をもとにした課題設定のポイント
以下のように分析しながらリハビリ課題を設定しましょう:
- 歩行速度が遅いが歩行率が高い → 歩幅が小さく、筋力や体幹の不安定性が原因か?
- 歩行率が低いが歩幅はある → リズム障害や注意力の問題を疑う
- 歩行率が不安定 → 認知的要因や感覚入力のズレが背景にあるかもしれない
このように、速度×歩行率の組み合わせで原因分析し、リハビリ方針を調整することが、臨床的には非常に重要です。
まとめ
- 10m歩行テストはADLやQOLの予測に役立つ
- 歩行速度は移動能力の指標、歩行率はリズムや神経機能の指標
- 両者を組み合わせた評価が、個別性の高い課題設定につながる
歩行速度だけでなく、歩行率にも目を向けることで、より精度の高いリハビリ評価と課題設定が可能になります。
患者一人ひとりに合った「歩き方」を支援するためにも、両者の評価を日々の臨床に取り入れていきましょう。
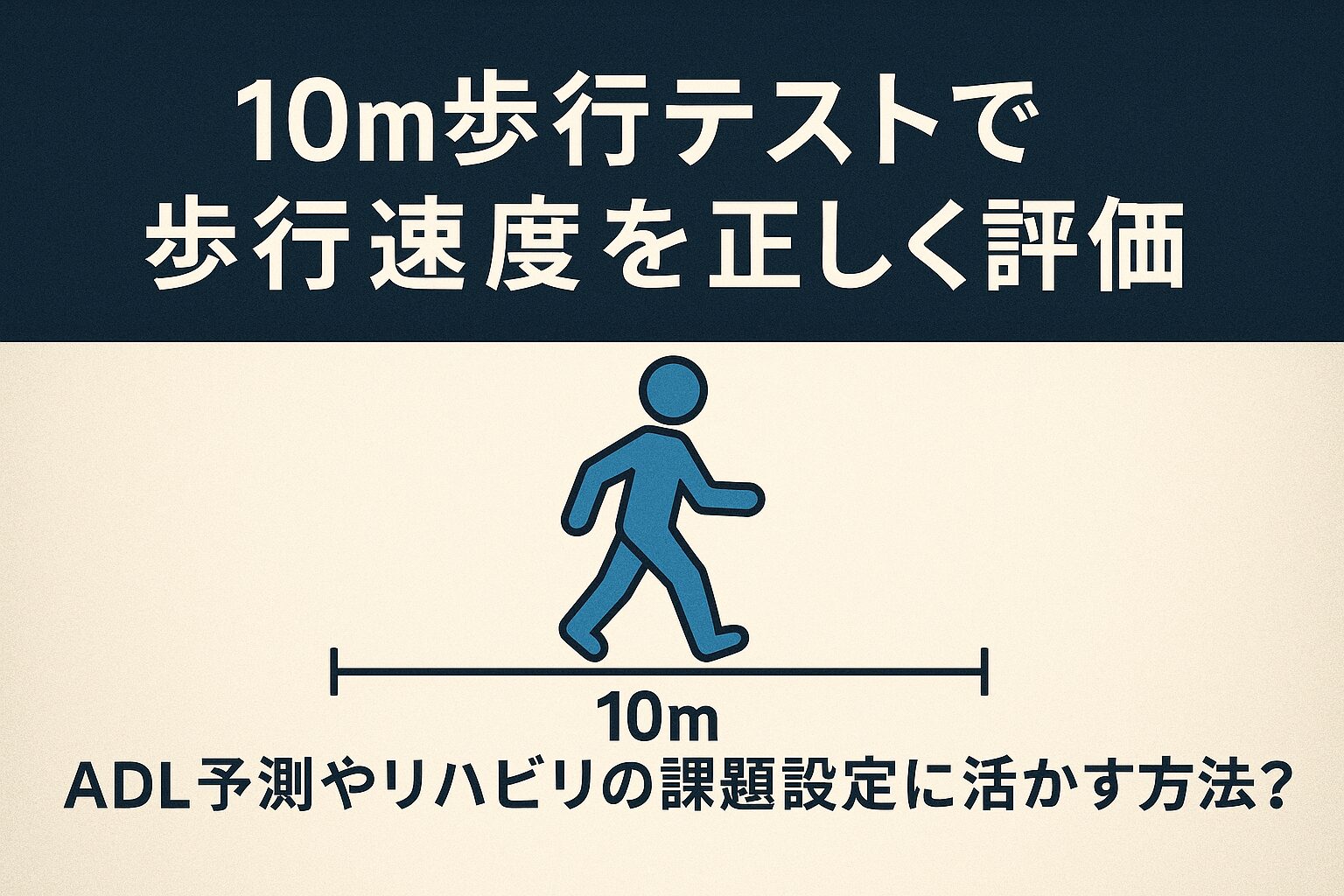


コメント