はじめに|歩行分析は“視点の整理”で変わる
歩行分析は理学療法士にとって欠かせない評価のひとつです。
しかし「ただ眺めているだけ」で終わってしまい、介入につながらないことも少なくありません。
私自身も臨床初期は「結局どこを見れば良いのか」で迷うことが多くありました。
そこで今回は、歩行分析の基本となる5つの視点と、歩行周期ごとにチェックすべきポイントを整理しました。
歩行分析で見るべき5つの視点
- 姿勢(アライメント)
頭部・体幹・骨盤の位置関係を確認し、左右差や傾きを観察します。 - 荷重の移動(重心・支持基底面)
体重移動がスムーズか、左右の偏りがないかを確認します。 - 関節運動(関節角度・タイミング)
股・膝・足関節の動きが適切なタイミングで出ているかを観察します。 - 筋活動(どの筋が働いているか)
立脚中の中殿筋、遊脚期の前脛骨筋など、必要な筋が機能しているかを推測します。 - 代償動作(本来の動きとの違い)
骨盤挙上・体幹側屈・過剰な腕振りなど、代償動作から機能低下の背景を考えます。
歩行周期ごとの観察ポイント
立脚期(支持性を確認)
- 初期接地〜荷重応答:踵接地の有無、前脛骨筋による背屈制御、体幹の安定
- 立脚中期:重心移動のスムーズさ、中殿筋の働き、膝伸展保持
- 立脚後期:踵離地のタイミング、股関節伸展の確保、足関節背屈の可動域
遊脚期(振り出しを確認)
- 遊脚初期:股関節屈曲の開始、膝屈曲角度、つま先クリアランス
- 遊脚中期:股関節屈曲角度、骨盤の前方回旋、つま先クリアランス
- 遊脚後期:膝伸展のタイミング、足関節背屈保持、次の初期接地への準備
臨床での応用
- 立脚期では「どれだけ安定して荷重を支えられるか」を評価します。
- 遊脚期では「つまずかずに次の一歩を準備できるか」を確認します。
- 代償動作が見られたら「なぜ出ているのか(筋力低下・ROM制限など)」を必ず考えるようにします。
まとめ|5つの視点+歩行周期で整理する
歩行分析は「姿勢・荷重・関節・筋・代償」の5つの視点で整理することができます。
さらに歩行周期に当てはめて確認することで、どの場面で問題が出ているのかをより明確に捉えられます。
今後は立脚期と遊脚期に分け、それぞれの局面で見られる特徴や原因について詳しく解説していきます。


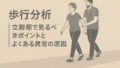
コメント