はじめに|立脚期は「支持性」を評価する重要な場面
歩行分析に取り組むとき、立脚期の評価に迷った経験はありませんか?
私自身も臨床初期は「膝折れがあるけれど、どこを見れば原因が分かるのか」と悩んだことが多くありました。立脚期は歩行周期の約60%を占め、体重を支える「支持性」を評価する重要な場面です。異常を見逃すと転倒リスクや歩行効率の低下に直結します。
この記事では、立脚期を3つの局面に分けて「どこを見るか」と「よくある異常の原因」を整理します。
① 初期接地〜荷重応答(Initial Contact〜Loading Response)
- どこを見るか
踵接地の有無、前脛骨筋の活動による背屈制御、体幹や骨盤の安定性を確認する。 - よくある異常の原因
- 足関節背屈制限により踵接地できず前足部接地になる
- 前脛骨筋の筋力低下で足がパタッと落ちる(フットスラップ)
- 体幹筋(脊柱起立筋・多裂筋・腹斜筋群など)の安定性低下で接地時にふらつく
② 立脚中期(Mid Stance)
- どこを見るか
重心が支持脚にスムーズに移動しているか、中殿筋の働きで骨盤が水平に保たれているか、膝が安定して伸展保持できているか、さらに体幹伸展位が維持できているかを確認する。 - よくある異常の原因
- 中殿筋筋力低下によるTrendelenburg徴候
- 大腿四頭筋筋力低下で膝折れが生じる
- 膝OAや疼痛による膝伸展保持不良
- 体幹伸展位の保持不良、骨盤の水平性低下(体幹筋協調性の不足によるバランス不良)
③ 立脚後期(Terminal Stance〜Pre Swing)
- どこを見るか
踵離地のタイミング、股関節伸展の確保、足関節背屈の可動域を観察する。 - よくある異常の原因
- 下腿三頭筋の短縮で踵離地が早くなる
- 股関節伸展制限で歩幅が小さくなる
- 大腿四頭筋の弱化により蹴り出しが不十分
臨床応用のポイント
立脚期の異常は「支持性の低下」と直結します。
例えば、膝折れがある場合は立ち上がりや階段昇降でもリスクが高くなり、歩行自立の判断にも影響します。
また、体幹や骨盤の不安定性があると、全体の歩行効率が低下し、疲労や転倒のリスクを増大させます。
評価したポイントをADLと関連づけて考えることで、転倒予防やリハビリ介入につながります。
まとめ|立脚期は歩行の安定性を左右する
立脚期は「荷重を支える」という歩行の基本的な役割を担っています。
初期接地〜後期までを局面ごとに整理して観察すれば、原因の特定と介入に直結します。
私自身も病棟で、立脚中期に中殿筋の弱さや体幹の伸展保持不良を見逃すと、歩行自立の判断が遅れたり、転倒リスクにつながることを経験しました。逆に視点を整理して評価するようになってからは、問題を早期に見つけ、ADL指導や運動療法に活かしやすくなりました。
次回は「遊脚期」に注目し、振り出しの局面で見るべきポイントと異常の原因について解説していきます。
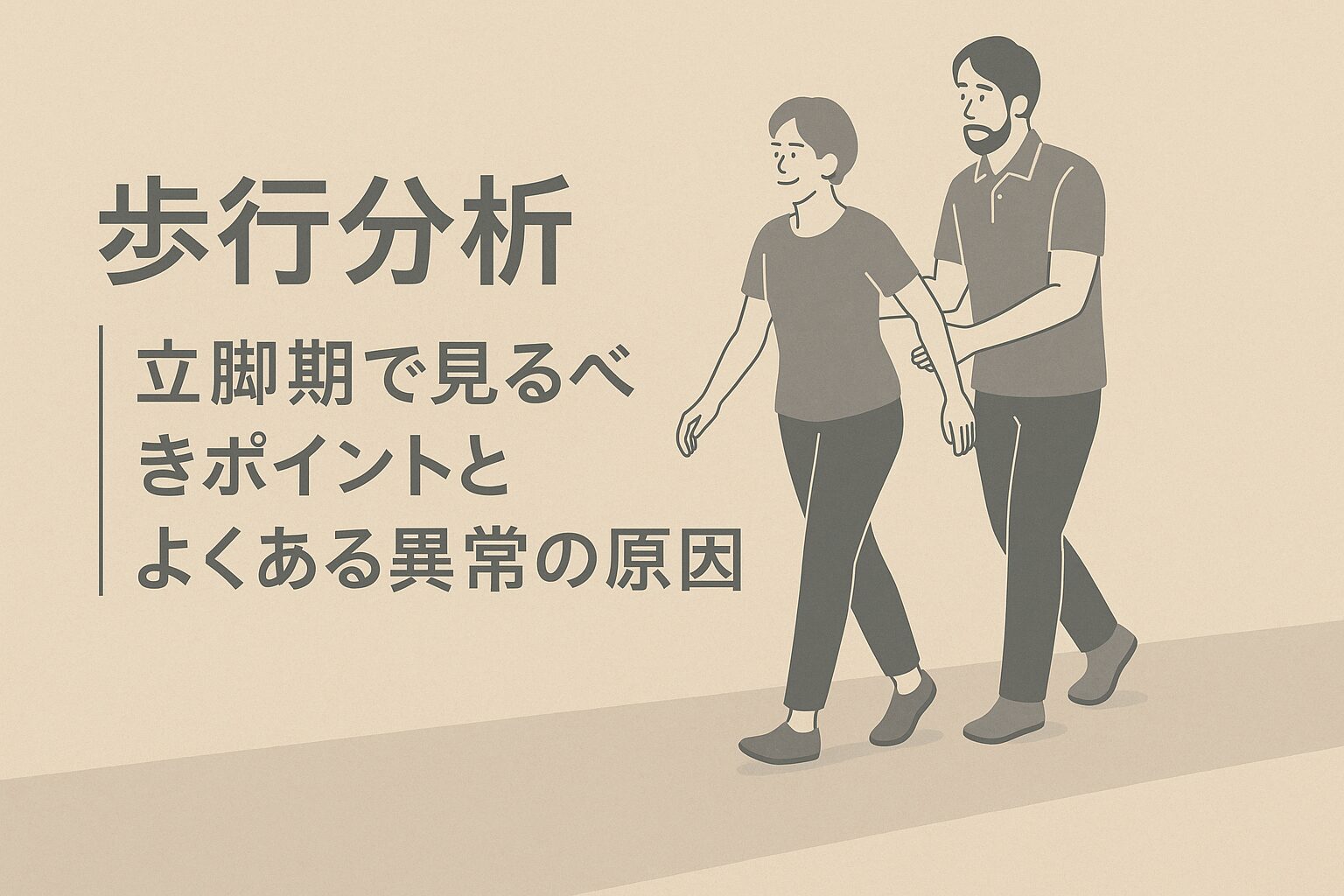


コメント