はじめに|働くフィールドに迷う理学療法士へ
理学療法士として働いていると、「急性期・回復期・生活期のどこで働くべきか」と迷うことはありませんか?
それぞれのフィールドは対象や役割が異なり、学べることや求められるスキルも違います。
私自身もキャリアの途中で「自分にはどの領域が合っているのだろう」と悩んだ経験があります。そこで本記事では、各領域の特徴やメリット・デメリットを整理し、選び方のポイントを解説します。
① 急性期リハビリの特徴
- 役割
手術直後や急性疾患後の患者を対象に、早期離床や合併症予防を行う。 - 対象
整形外科術後、脳卒中急性期、心疾患など。 - メリット
医学的知識が深まる。医師や多職種と連携する機会が多く、臨床スキルが磨かれる。 - デメリット
回転が速く1人に関わる期間が短い。業務が忙しく、体力的な負担が大きい。
② 回復期リハビリの特徴
- 役割
集中的なリハビリを通して、生活動作の自立をめざす。 - 対象
脳卒中後、整形外科術後、大腿骨骨折など。 - メリット
ADL訓練や歩行訓練が豊富で、患者や家族と長期間関われる。リハの成果が見えやすい。 - デメリット
退院支援やカンファレンスが多く、書類業務の負担が大きくなることもある。
③ 生活期リハビリの特徴
- 役割
在宅や施設での生活を支え、介護予防やQOL維持をサポートする。 - 対象
高齢者、慢性疾患、維持期の利用者。 - メリット
長期的に関われる。生活に直結した介入ができ、地域とのつながりが強まる。 - デメリット
医学的な処置は少なく、スキルアップ感が薄いと感じる人もいる。
④ 自分に合った働き方を選ぶポイント
- キャリアの軸を決める
「医学的知識を深めたい」なら急性期。
「ADL訓練に強くなりたい」なら回復期。
「地域に根差して生活支援したい」なら生活期。 - 働き方のスタイルを考える
体力、勤務時間、ワークライフバランスを考慮する。 - キャリアアップとの関連性
大学病院や専門病院で専門性を深めたいなら急性期。
教育や管理職をめざすなら回復期や生活期の経験も役立つ。
まとめ|キャリアは一つではない
急性期・回復期・生活期は、それぞれ役割も魅力も異なります。
大切なのは「今の自分が何を学びたいか」「どんな働き方をしたいか」という視点です。
私は回復期を中心にキャリアを積んできましたが、慢性期の病院、非常勤で訪問リハやデイケア、老健、自費リハビリなども経験しました。多様な場を経験することで、それぞれの強みや課題を比較でき、より広い視点で患者さんや利用者さんと向き合えるようになりました。
キャリアは一つに固定されるものではなく、ライフステージや興味に合わせて柔軟に変化していくものです。迷ったときは一度整理して、自分のキャリアプランと照らし合わせてみましょう。
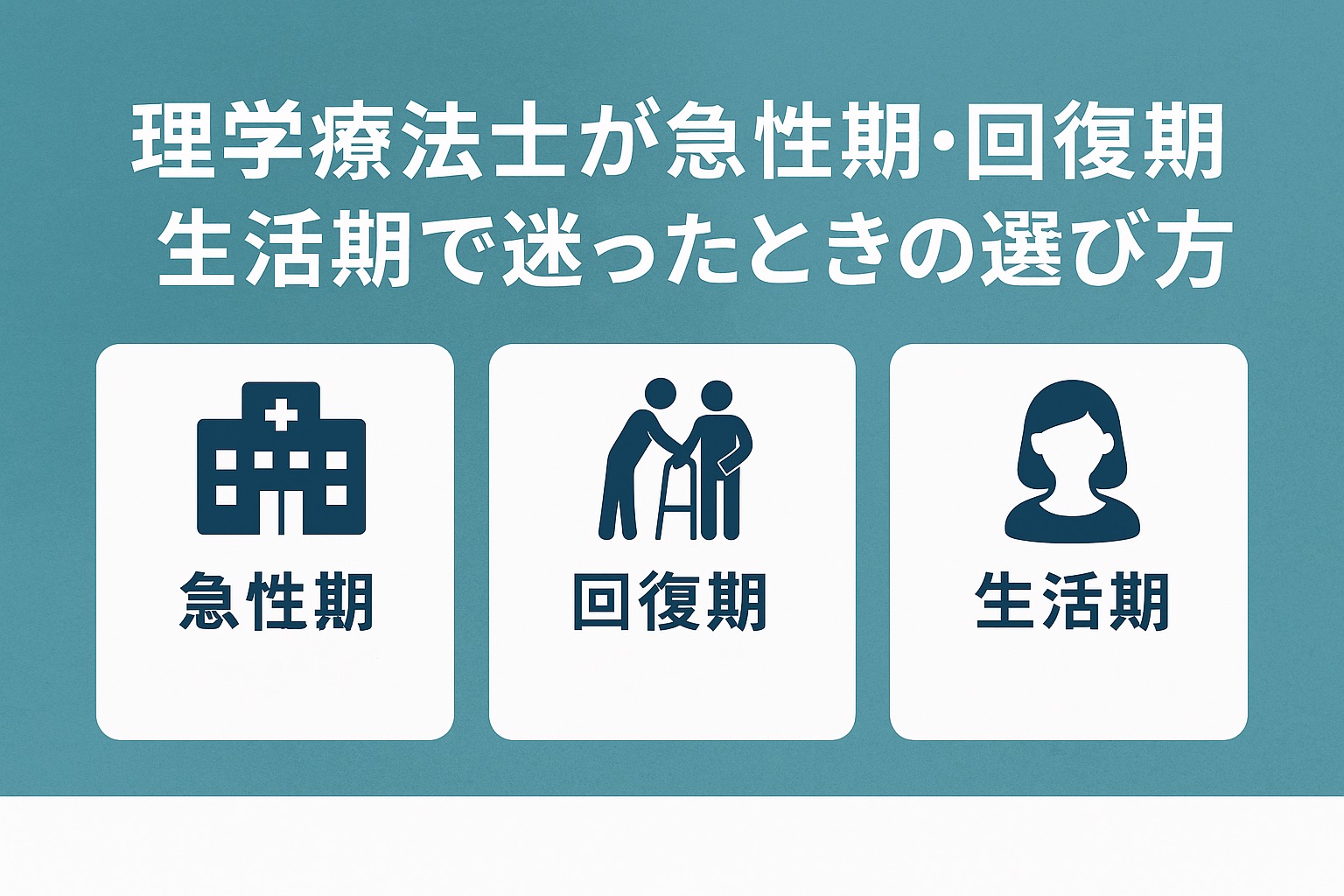

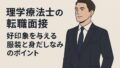
コメント