はじめに
理学療法士として臨床に立つと、動作を「どう見て、どう解釈するか」に迷う場面は少なくありません。評価や治療の基盤となるのは、動作を丁寧に観察する力です。この記事では、観察力を鍛えるための動作分析の基本と、臨床現場で役立つ実践のヒントをまとめます。
動作分析の基本ステップ
- 全体像を捉える(目的・結果・スムーズさを確認)
- フェーズに分ける(開始→移行→終了/歩行なら立脚期・遊脚期など)
- 異常所見を特定する(膝折れ・つま先の引っかかり・過剰な体幹運動 など)
- 原因を仮説化する(筋力・可動域・疼痛・協調性・感覚入力など多面的に)
- 介入に落とし込む(検証→再評価→修正のサイクルに組み込む)
各ステップのポイント解説
1. 全体像を捉える
最初に細部へ入り込むのではなく、「その動作は目的を満たせているか」「全体としてスムーズか」「安全か」を確認します。
- 例:立ち上がりなら「手を使わずに一連で行えるか」「ふらつきなく立位へ移行できるか」。
- 歩行なら「歩速・歩幅・リズム(テンポ)」「左右差」「疲労による変化」。
ここでの目的は「問題がありそうな局面のあたりを付ける」ことです。全体像が掴めると、次のフェーズ分解で観察の焦点が定まります。
2. フェーズに分ける
同じ動作でも、開始・移行・終了のように段階化すると観察が立体的になります。歩行なら初期接地→荷重応答→立脚中期→立脚後期→遊脚期、立ち上がりなら開始(前傾形成)→離殿→伸展→安定化といった区切りです。
- 例:階段昇降で「踏み込み時(立脚)に膝外反が強い」「離地後(遊脚)に足尖が落ちる」など、“いつ起きるか”を言語化できると原因推定が加速します。
フェーズ化は、チーム内共有や記録の精度向上にも役立ちます。
3. 異常所見を特定する
フェーズを意識して観察すると、異常が現象レベルで見つけやすくなります。
歩行でよくある現象例
- 膝折れ(立脚早期〜中期での膝過屈曲)
- トークリアランス不足(遊脚期の足尖引っかかり)
- 体幹の過度な側屈/回旋(代償として出現)
- 骨盤のドロップ(中殿筋機能低下の示唆)
- 歩隔の過大/過小、歩調の不整
歩行以外の動作でよくある現象例
- 立ち上がり時の前傾不足 → 重心移動が不十分で離殿できない
- 階段昇降時の踏み込みで膝外反が強い → 中殿筋や膝周囲の安定性不足
- 上肢挙上で肩甲骨が過度に挙上・前傾 → 肩甲帯安定筋群の機能低下
- ベッド移乗で過剰な体幹の側屈や回旋 → 体幹筋協調性や股関節安定性の不足
ここではまだ原因断定はせず、「何が」「どの局面で」「どのくらいの頻度・強さで」起きるかを、繰り返し観察して精度を上げていきます。
4. 原因を仮説化する
異常所見を機能面に落として考えます。単一要因より複合要因が多い点に注意します。
代表的な視点:
- 筋力:中殿筋・大腿四頭筋・前脛骨筋・下腿三頭筋など局在的低下
- 関節可動域(柔軟性):股伸展・足関節背屈・膝伸展/屈曲の不足
- 疼痛:痛み回避による運動学的な変容(例:前傾抑制→立ち上がり困難)
- 協調性・タイミング:筋活動の順序や共同運動の不適切さ
- 感覚入力・バランス:固有感覚・前庭・視覚の統合不良
例:遊脚期のトークリアランス不足
- 仮説A:前脛骨筋の筋力低下
- 仮説B:股関節屈曲・膝屈曲のタイミング不全
- 仮説C:立脚後期の足関節背屈制限→十分な推進が得られず振り出し低下
このように局面×現象×機能で因果を仮説化すると、次の介入設計が論理的になります。
5. 介入に落とし込む(検証→再評価)
仮説に基づき、即時効果を確認できるテスト介入から始めます。
- トークリア不足に対し足関節背屈可動域の即時改善(モビライゼーション/ストレッチ)→再歩行
- 立脚中期の膝折れに対し四頭筋賦活(クローズドチェーン練習)→再評価
- 骨盤ドロップに対し中殿筋筋力+体幹協調の課題練習→動画比較
効果が乏しければ仮説を修正します。(観察→仮説→介入→再観察)のサイクルを短く回すほど、臨床の精度が上がります。必要に応じて環境要因(床面・靴・杖・歩行補助具の設定)やADLの導線も同時に見直します。
実践で活きる観察のコツ
- まず“安全”に注目:バランス喪失・つまずき・疼痛のサインを最優先で把握する
- 1観点フォーカス法:1回目は体幹、2回目は骨盤、3回目は膝…と、観察ラウンドごとに部位を変えると見落としが減る
- 動画とスロー再生:主観を離れ、タイミングのズレや代償の出方を客観視できる
- 用語を揃える:チームで「立脚中期の膝折れ」など表現を統一すると、共有と介入が速くなる
- 患者の主観情報:怖さ・痛み・疲れやすい場面など“本人の感じ方”は原因推定の貴重なヒントになる
まとめ
動作分析は、
全体像 → フェーズ分解 → 異常所見 → 原因仮説 → 介入・再評価
という手順で整理すると、迷わず深掘りできます。
局面・現象・機能をつなぐ“言語化”が進むほど、治療設計は具体的になり、チーム連携もスムーズになります。明日からの臨床で、まずは「全体を見てから、局面ごとに一点フォーカス」を試してみてください。
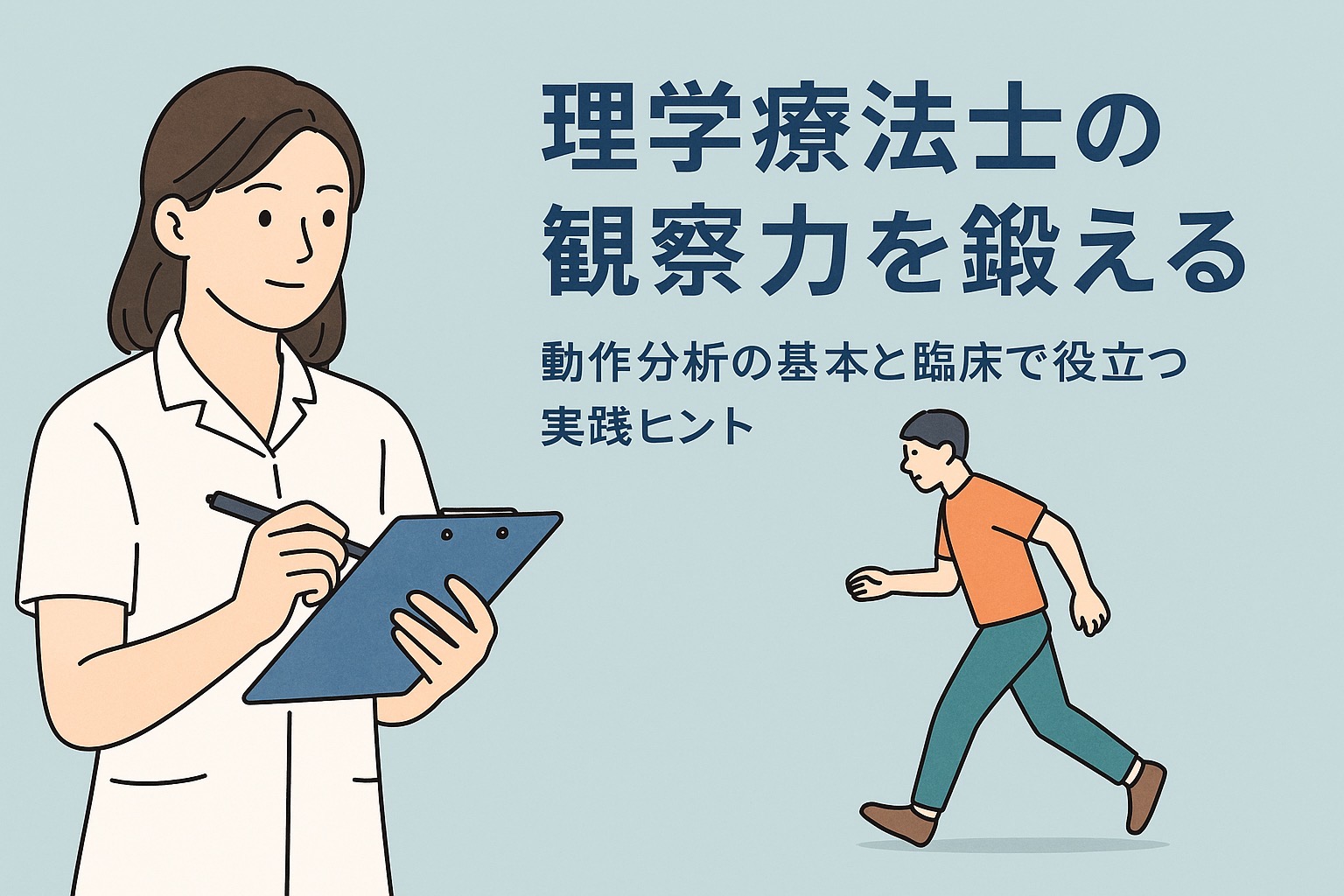


コメント