姿勢とバランス評価は臨床の第一歩
バランス評価は「立てるか・座れるか」を見るだけではありません。安定して保持できるか、外乱や動作に対応できるかまでを観察することで、転倒リスクや日常生活での自立度を予測できます。理学療法士にとって、姿勢とバランスの評価はリハビリの出発点と言えるでしょう。
バランスを捉える5つの視点
バランスを評価するときは、以下の5つの切り口で整理すると全体が見やすくなります。
- 支持基底面(BOS):足幅や手の支持で安定性が変化
- 重心(COM):どこに重心があるか、動作でどう移動するか
- 安定性限界:どこまで傾いても保持できるか
- 姿勢反応:立ち直り反応・パラシュート反応・ステップ反応の出方
- 代償手段:体幹の傾き、手の支持、過剰な動作など
座位での評価ポイント
- 静的座位:坐骨でしっかり座れるか。体幹の傾き、骨盤の前後傾、左右差を観察。
- 動的座位:前後・左右へのリーチができるか。外乱が加わったときに手を出して支えられるか。
- 臨床での注意:仙骨座りや片坐骨への偏りは、上肢の操作や呼吸・発声にも影響。私の経験でも、仙骨座りのまま長時間過ごす患者さんは肩の可動域制限や呼吸の浅さを伴うことが多く、早めの姿勢調整が有効でした。
立位での評価ポイント
- 静的立位:両脚→閉脚→タンデム→片脚の順で難易度を上げて確認。重心の揺れや代償動作を観察。
- 動的立位:方向転換、歩行開始、外乱(軽い押し)にどう反応するか。
- 姿勢反応:足関節戦略→股関節戦略→ステップ戦略へと移れるか。立ち直り反応・パラシュート反応・ステップ反応の観察は、転倒リスクを測るうえで特に重要です。
- 立ち直り反応:姿勢を崩しても正しい位置に戻ろうとする反応。
- パラシュート反応:前後左右に傾いたとき、手を伸ばして支えようとする反応。
- ステップ反応:重心が大きく崩れたときに、一歩踏み出して転倒を防ぐ反応。高齢者では出にくくなることが多く、転倒リスク予測の大切な評価ポイント。
観察のコツと臨床応用
- まず安全を確認:保持できるかよりも、転倒リスクや外乱への対応を優先的にチェック。
- 段階的に評価:座位→立位、安定→不安定と条件を変えて観察すると変化が見やすい。
- 本人の自覚を聴取:「怖さがある」「力が入らない」など主観情報も重要。
- 評価から介入へ:外乱反応が弱ければ、ステップ練習や動的課題で強化。仙骨座りなら、骨盤前傾保持や体幹アクティベーションを導入。
まとめ
座位と立位のバランス評価は、ただ「できる・できない」を確認するものではありません。支持基底面や姿勢反応、代償の仕方まで含めて捉えることで、転倒予測やリハビリ方針の精度が高まります。特に立ち直り反応・パラシュート反応に加え、ステップ反応の評価は転倒予防に直結する欠かせない観察ポイントです。
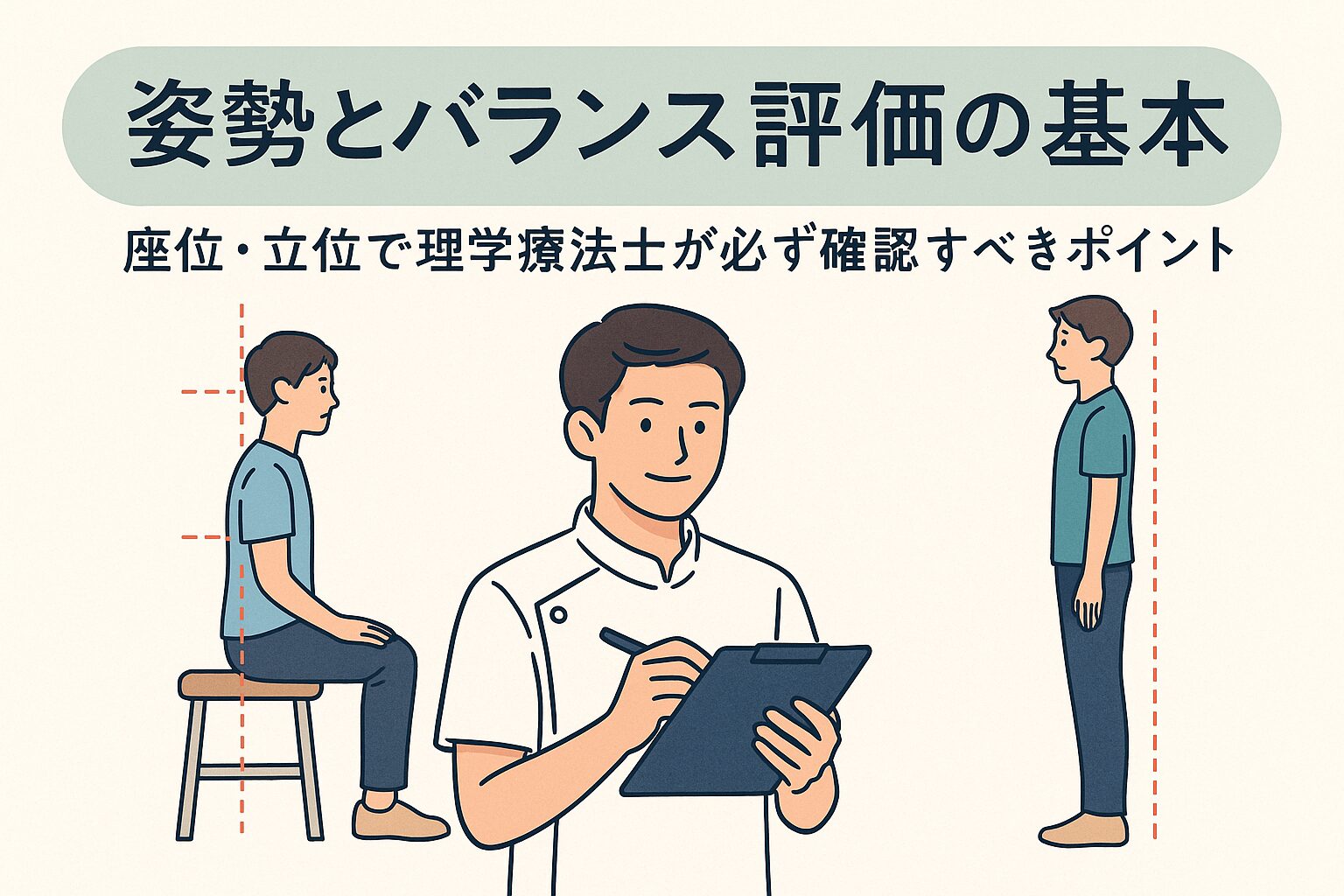


コメント