はじめに
高齢者の転倒予防において、立位バランスの評価は欠かせません。中でも Functional Reach Test(FRT) は、臨床現場で広く使われる簡便で信頼性の高い方法です。立位でどれだけ前方に手を伸ばせるかを測ることで、日常生活に直結する動的バランス能力を評価できます。この記事では、FRTのやり方と判定基準、さらに臨床での注意点について解説します。
Functional Reach Test(FRT)とは?
Functional Reach Test(FRT)は、1990年代に開発されたバランス評価法で、立位での安定性と転倒リスクを予測するための指標として活用されています。前方へのリーチ距離を測定するだけのシンプルな評価ですが、転倒との関連性が多くの研究で報告されており、リハビリテーションや地域包括ケアでも利用されています。
FRTのやり方(評価手順)
- 壁にメジャーを水平に設置する。
- 被験者を直立位に立たせ、足は肩幅程度に開く。
- 片腕を肩の高さまで前方に挙げ、中指先端の位置を「開始位置」として記録。
- 可能な限り前方に体幹を傾け、中指先端の位置を「到達位置」として記録。
- 到達距離(cm) = 到達位置 − 開始位置 を算出。
測定時の注意点
- 踵は床から離さない。
- 転倒に注意し、必ず見守りながら実施する。
- 代償動作(膝の曲げすぎ、体幹のひねりなど)が入らないように観察する。
判定基準(転倒リスクとの関連)
一般的に、到達距離が短いほど転倒リスクが高いとされています。
- 15cm未満: 高リスク
- 15〜25cm: 中等度リスク
- 25cm以上: 低リスク
年齢ごとの平均値(代表的な研究データ)
- 21〜39歳:38.5cm
- 40〜59歳:35.0cm
- 60〜69歳:31.2cm
- 70歳以上:27.0cm前後
加齢に伴ってリーチ距離は短くなり、70歳以上では25〜27cm程度が目安となります。
生活環境による違い
- コミュニティ居住高齢者(在宅で自立して生活している人): 平均 25〜30cm
- 非コミュニティ高齢者(施設入所・介護サービス継続利用など): 平均 15〜20cm
臨床での注意点
- 身体特性の影響: 身長や上肢長が長いほどリーチ距離は伸びやすい。
- 感覚機能の影響: 視覚・前庭・固有感覚の異常があるとバランス保持に影響。
- 代償動作の存在: 股関節や膝を大きく曲げて前に倒れる場合、正しいバランス能力を反映しない。
- 他の評価との併用: Berg Balance Scale(BBS)、Timed Up and Go Test(TUG)などと組み合わせると、より正確に転倒リスクを評価できる。
まとめ
Functional Reach Test(FRT)は、短時間で実施でき、転倒予測に有効なバランス評価法です。15cm未満は高リスクとされ、早期からの介入が望まれます。年齢や生活環境による基準値を踏まえたうえで解釈することが大切です。
ただし、FRT単独で転倒リスクを判断するのは不十分です。他のバランス評価や日常生活動作の観察と合わせて、総合的に判断することが重要です。臨床現場から地域ケアまで、幅広い場面で活用できる評価法として、ぜひ取り入れてみてください。
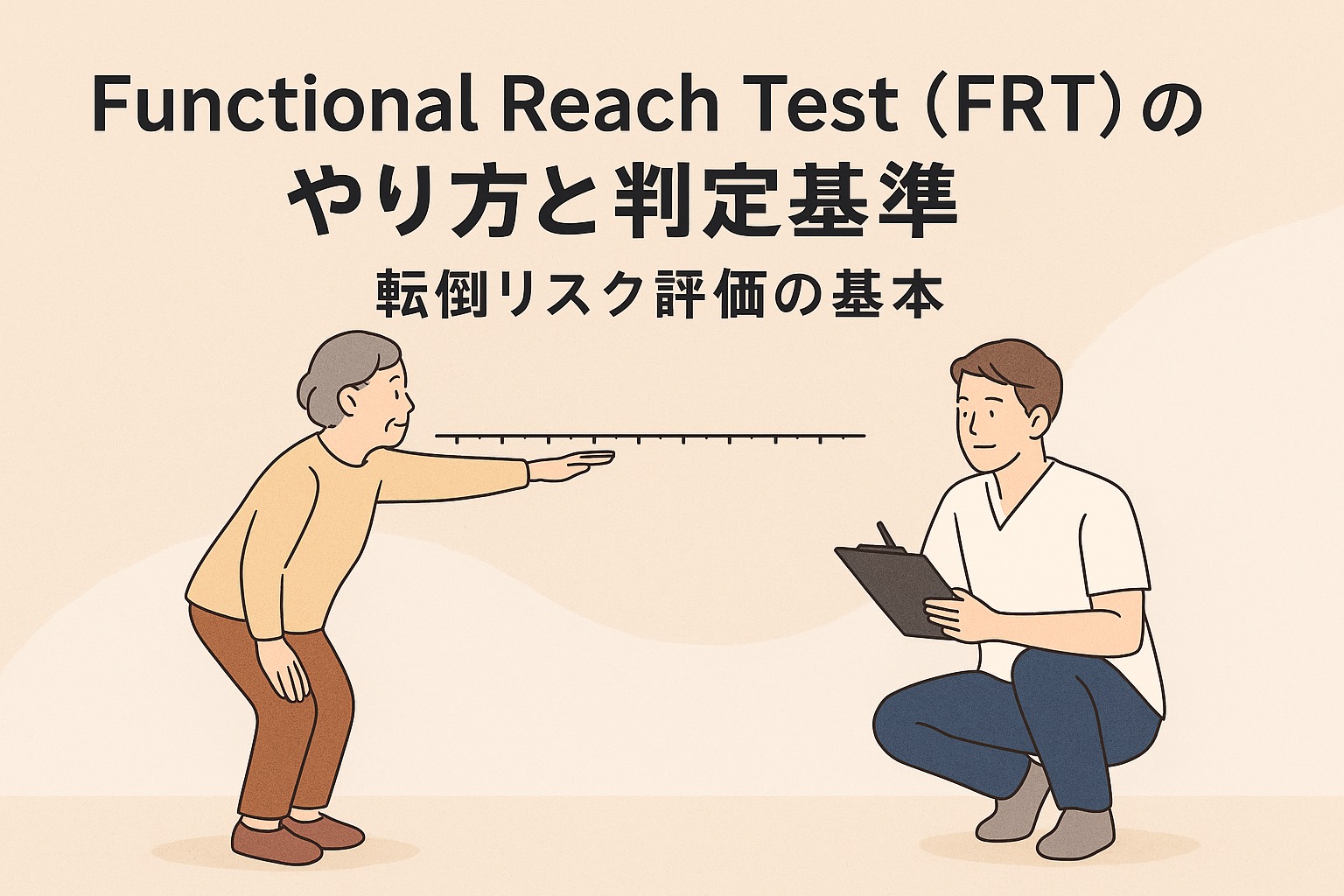


コメント