はじめに
体幹の安定性は、歩行や立ち上がりといった日常動作の土台となる重要な要素です。体幹が安定していなければ、四肢の動きがどれほど良くても効率的な運動はできません。理学療法士にとって「体幹機能評価」は、患者さんの動作を理解し、リハビリの方向性を決めるうえで欠かせないスキルです。この記事では、体幹の働きをバランスと安定性の観点から整理し、臨床で使える評価のポイントを分かりやすく解説します。
体幹機能評価の目的と意義
体幹機能評価は、単に筋力を測るものではありません。目的は「姿勢保持や動作の中で、体幹がどのように働いているか」を明らかにすることです。主な目的は次の3つです。
- 姿勢保持能力を確認する(座位・立位での安定性)
- バランス戦略を見極める(Ankle・Hip・Step戦略の使い方)
- 体幹と四肢の連動を把握する(運動連鎖や協調性の観察)
これらを評価することで、転倒の原因や歩行の不安定さ、さらにはADL動作時の姿勢崩れなどの背景が見えてきます。
体幹機能評価の5つの基本視点
体幹機能を総合的に見るには、次の5つの視点を押さえておくと整理しやすくなります。
- 静的姿勢の安定性(座位・立位で軸が保たれているか)
- 骨盤・脊柱アライメントの確認(骨盤の傾き・脊柱のカーブ)
- 重心位置と姿勢制御(前後・左右のバランスの取り方)
- バランス反応の出方(リーチ動作や外乱刺激への対応)
- 体幹筋群の働きと協調性(深部筋・表層筋の連動やタイミング)
これらを観察することで、体幹が「過剰に固定されている」のか「不安定すぎる」のかを判断しやすくなります。
静的姿勢の安定性とアライメントを観察する
まずは静止姿勢での安定性を確認します。
- 頭部から骨盤まで軸が通っているか
- 骨盤の前傾・後傾・側方傾斜はないか
- 肩の高さや脊柱のカーブの左右差
この段階で姿勢が崩れている場合、筋力だけでなく感覚入力や支持面の影響も考えられます。座位での不安定さが強い場合は、まず骨盤位置や支持面の調整から始めると効果的です。
動的体幹制御と重心移動の評価
次に、動作中の体幹制御を観察します。起立動作、前方リーチ、方向転換などの動作を通して次の点を確認します。
- 骨盤や体幹が動作にスムーズに追従しているか
- 下肢との連動が取れているか
- 不必要に体幹を固めていないか
体幹の動きが遅れたり、逆に固定されすぎていると、下肢の代償運動や筋緊張の上昇を招き、動作効率が低下します。体幹が「安定して柔軟に動けるか」を見ることがポイントです。
バランス反応の評価
軽い外乱刺激(押す・引く)や不安定座位での反応を観察し、姿勢制御能力を確認します。
- どの戦略(Ankle・Hip・Step)を使って姿勢を保っているか
- 反応の速さと適切さ
- 支持基底面(足底・坐骨など)の使い方
反応が遅い場合は感覚入力の問題、反応が過剰な場合は体幹固定や恐怖心などの影響も考えられます。
体幹筋群の働きと協調性
腹横筋・多裂筋・骨盤底筋などの深部筋と、腹直筋・脊柱起立筋などの表層筋の協調性を確認します。特に次のポイントを観察します。
- 軽い四肢動作時の体幹反応
- 呼吸や発声との連動
- 筋活動のタイミング
強さよりも「いつ・どのように働くか」を見ることが大切です。腹横筋の働きが遅れると、体幹安定性が低下し、腰部痛やバランス障害を引き起こしやすくなります。
歩行・ADL動作との関連
体幹の安定性は、歩行や立ち座り動作、方向転換などの基本動作に直結します。
- 骨盤回旋と体幹の連動
- 歩行中の重心移動のスムーズさ
- 固定的姿勢による動作のぎこちなさ
体幹の評価を通して、歩行効率やADL動作の改善ポイントを明確にできます。特に、体幹と四肢の協調性が整うと、動作の安定感とエネルギー効率が向上します。
まとめ|体幹機能は“姿勢と動作をつなぐ鍵”
体幹機能評価の目的は、筋力を数値化することではなく、「姿勢と動作の関係を明らかにすること」です。静的・動的・バランス・協調性の観点から体幹を観察することで、より精度の高い動作分析と介入につなげられます。次回は、「姿勢と骨盤アライメントの評価法」について、臨床で活かせる具体的な見方を解説します。
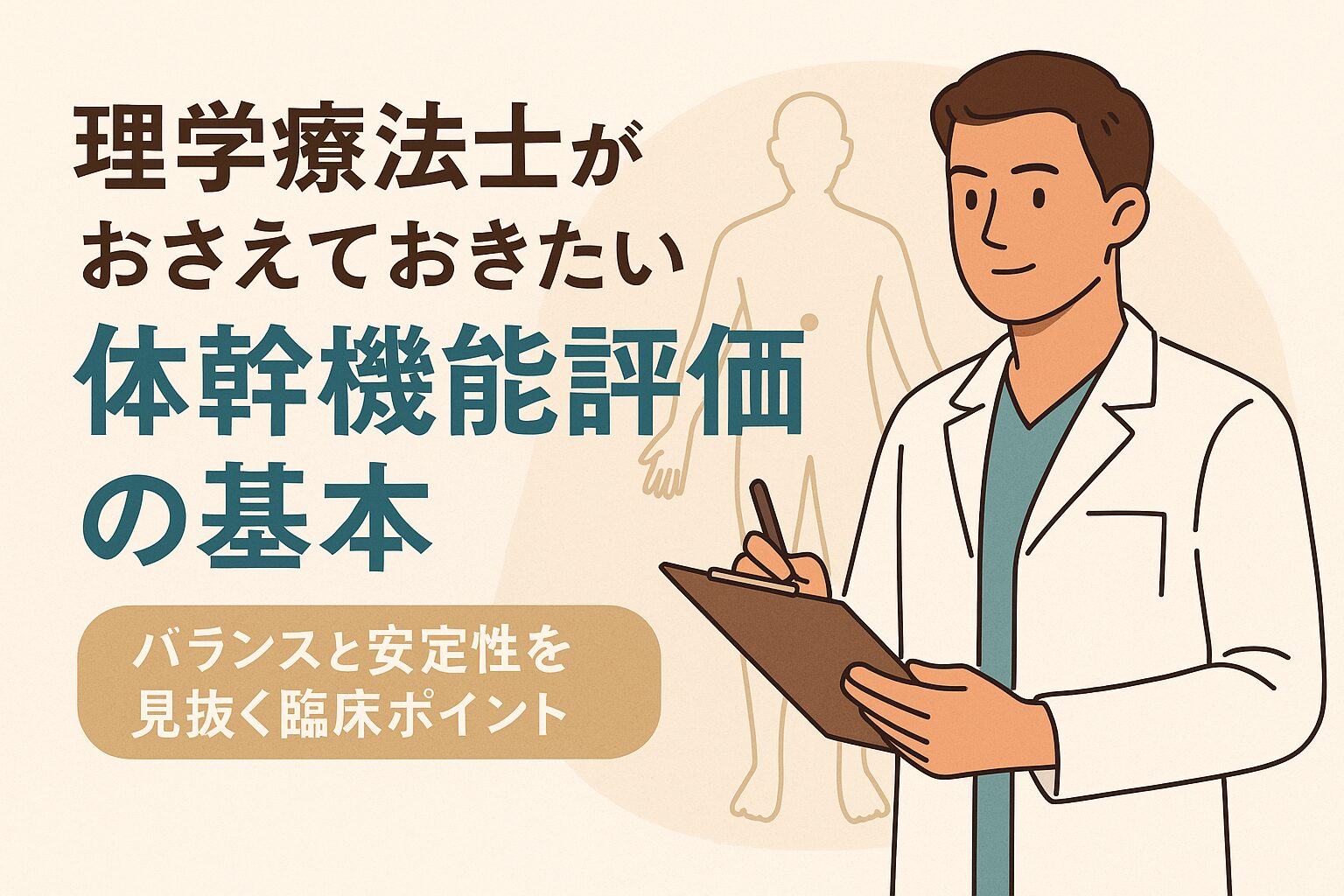


コメント