はじめに
理学療法士として働く中で、「残業が多くて疲弊している」「もっとワークライフバランスを大切にしたい」と感じたことはありませんか?
残業の少ない職場を選ぶことは、長く働き続けるためにとても重要です。しかし、求人票や見学だけでは本当の働き方を見抜くのは難しいのが現実です。そこで今回は、残業の少ない職場を見極めるための10のチェックリストを紹介します。私自身の経験も交えて解説しますので、転職や職場選びの参考にしてください。
残業が少ない職場を見抜く10のチェックリスト
- 勤務時間の実績と運営状況
- スタッフの退勤時刻の平均
- カンファレンスや会議の時間帯
- 書類業務の負担と仕組み化
- シフト管理の実態
- 業務効率化の取り組み
- 有給休暇の取得状況
- 管理職のマネジメント方針
- 離職率や人員の安定度
- 外部からの情報収集
各チェックポイントの解説
1. 勤務時間の実績と運営状況
求人票に記載されている勤務時間はあくまで目安です。大切なのは、実際に「定時で仕事が終わっているか」「シフトどおりに回っているか」を確認すること。私は見学・面接時に「普段は何時ごろに帰れていますか?」「予定通りに患者さんの枠は回せていますか?」と質問したことで、残業の実態を直接知ることができました。
2. スタッフの退勤時刻の平均
個人差ではなく“全体の傾向”を捉える視点です。誰かは定時で帰れても、部署全体として遅くなりがちなら残業文化が根付いている可能性があります。スタッフに「皆さんは何時ごろに退勤されることが多いですか? 月の平均残業はどのくらいですか?」と具体的に尋ねると、雰囲気も含めて実態が見えてきます。
3. カンファレンスや会議の時間帯
業務終了後にカンファレンスを設定している職場は、残業が常態化しやすい傾向です。一方で、現在の職場では朝の15分を使って必要事項を共有する“朝カンファレンス”を業務内に組み込む形へ改善し、業務後に残る必要がほとんどなくなりました。
つまり「会議をいつ行うか(業務時間内か外か)」が残業の有無に直結します。
4. 書類業務の負担と仕組み化
リハビリは書類業務が多く、ここが非効率だと残業に直結します。電子カルテ、定型文・テンプレート、音声入力などの導入状況を確認しましょう。紙ベースで個人任せだと負担増になりやすい一方、フォーマット化と入力補助が整っている職場は、業務時間内で完了できる体制が作られています。
5. シフト管理の実態
「人が足りずにシフトが回らない」「休憩が削られる」といった状況は、残業を生みます。作成者が誰か、見直し・調整の頻度、急な欠員時のヘルプ体制(非常勤・派遣・兼務)があるかを確認しましょう。シフト作成が透明で、前月中に確定している職場は安定しやすいです。
6. 業務効率化の取り組み
ルーチンの棚卸しやタスク分担、タイムブロッキング、タスク可視化(ボード・スプレッドシート)など、具体的な改善の仕組みがあるかを見ます。現場からの改善提案が採用される文化の有無も、残業削減の鍵になります。
7. 有給休暇の取得状況
有給が取りやすい職場は、業務に余裕がある職場です。「取得率」「半日有給の可否」「直前申請の扱い」など運用の実態を確認しましょう。取得率が高い=シフトと業務が回っている証拠であり、残業の少なさとも相関します。
8. 管理職のマネジメント方針
管理職が「時間内で終える」文化を重視しているかは非常に重要です。上長が率先して定時退勤し、会議を業務内に収め、タスクの優先順位付けを明確にする職場は、残業が少ない傾向があります。逆に「残るのが美徳」だと、業務が終わっても帰りづらい雰囲気が生まれます。
9. 離職率や人員の安定度
求人が常時出ている・入れ替わりが激しい職場は、一人あたりの負担が増え残業に直結します。定着率、平均勤続年数、直近1年の離職人数などを確認し、配属予定部署の状況も合わせて聞いておくと安心です。
10. 外部からの情報収集
求人票や短時間の見学だけでは、内部事情は見えにくいもの。実際に働いている理学療法士からのヒアリングや、転職エージェント経由の情報が役立ちます。私もエージェントと現場スタッフの両方から話を聞き、「残業は本当に少ない」と確信して応募先を絞れました。
具体的な比較・選び方は、こちらの内部リンクにまとめています:
👉 理学療法士向け転職サイト比較ページ
まとめ
残業の少ない職場を見抜くには、表面的な求人情報だけでなく、運営実態・会議の時間帯・書類の仕組み化・有給運用・人員安定度などを複合的に確認することが重要です。見学や面接では具体的な質問を用意し、外部情報も取り入れながら、自分に合った職場を選びましょう。無理のない働き方は、臨床の質や学習時間、私生活の充実にもつながります。
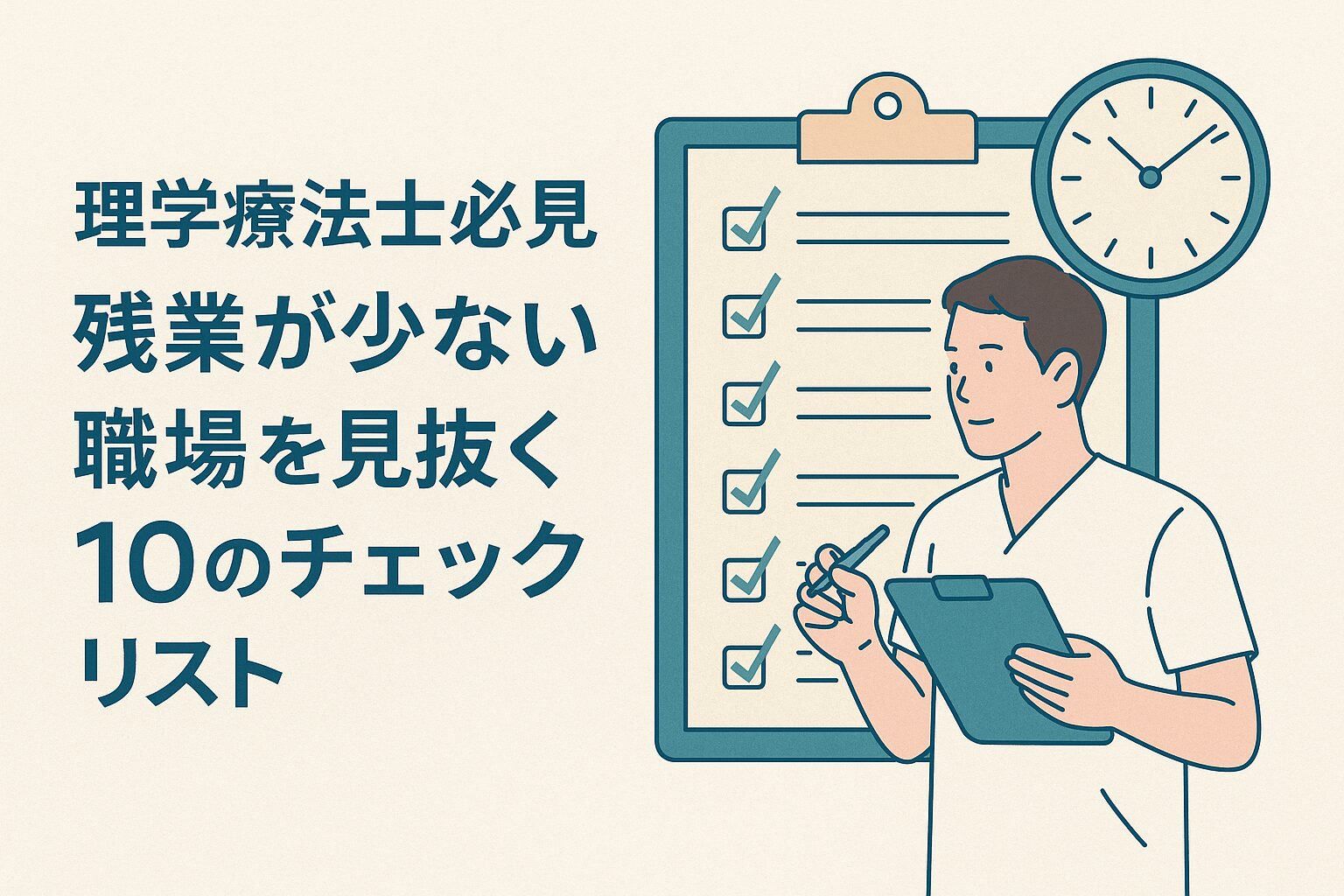


コメント