職場で同僚のモチベーションに左右されて、気持ちが疲れてしまうことはありませんか?
「自分だけ頑張っている気がする」「やる気のない人を見るとイライラする」——そんな思いを抱く理学療法士は少なくありません。
実はこの状態は、他人の行動に評価軸を置く“他人軸”になっているサインです。
自分軸を持つことがストレス軽減のカギ
他人の行動や態度はコントロールできませんが、自分の受け取り方・反応は変えられます。
「自分はどうありたいか」「どんなリハビリを提供したいか」という自分軸を明確にすると、周囲に振り回されにくくなり、日々のストレスもぐっと減ります。
- 相手に意識が向いたら「自分は今、何を最優先にするか」に視点を戻す
- 今日の業務目標(例:安全・機能・ADLのうち何を重視するか)を朝のうちに決める
- 比較ではなく、昨日の自分との小さな差分に注目する
同僚の行動に影響されないための思考整理術
同僚が手を抜いているように見えると、つい比較してしまいがちです。比較は疲労を増やすため、事実と感情を切り分けて認知を整理しましょう。
事実と感情を切り分ける
- 感情の表現:「〇〇さんはやる気がない」
- 事実の記述:「〇〇さんの記録が予定より30分遅れ、午後のリハ介入を14:30に開始」
感情ではなく事実を言語化することで、対処の選択肢(リスケ、応援依頼、フロー見直し等)が見えます。
上司への相談は「感情」ではなく「事実+影響」で伝える
同僚の行動が原因で自分や患者さんの業務に支障が出ている場合は、抱え込まずに上司へ相談しましょう。
ここで重要なのは、同僚の性格や態度を非難するのではなく、事実と業務への影響を具体的に伝えることです。
(この段落は「同僚のことを上司に報告する」場面をわかりやすく説明しています)
NG:「〇〇さんがやる気なくて、全然動きません!」(感情的で抽象的)
OK:「本日13:30時点で、〇〇さんの記録作業が30分遅延し、14:00開始予定の◯◯様・△△様のリハ介入がいずれも未実施となりました。患者さんのスケジュール再調整が必要です。」
このように、事実(いつ・何が・どれだけ)+影響(未実施・遅延・再調整が必要)を示すと、上司は状況を客観的に把握できます。
その結果、建設的な改善(人員調整、記録手順の見直し、役割分担)につながります。
自分の努力が報われないと感じたときに見直すポイント
- 目的の再設定:評価基準を「他人の反応」から「患者アウトカム/自分の成長」に戻す
- 可視化:介入目標・提供内容・小さな達成を簡易ログに残す(主観のブレを減らす)
- 環境調整:役割の偏りが続く場合は、配分の見直しを上司に提案(事実ベースで)
まとめ|他人を変えるより、自分の反応を整える
- 自分軸(今日の目的・優先順位)を明確にして、比較のループから抜ける
- 事実と言葉を整え、必要時は上司へ「事実+影響」で相談する
- 努力の評価軸を「患者アウトカム」と「昨日の自分比」に置く
同僚のやる気に振り回されないためのコツは、他人を変えることではなく、自分の認知と行動を整えること。
自分のペースを取り戻せば、心の消耗は大きく減り、臨床の質も安定します。
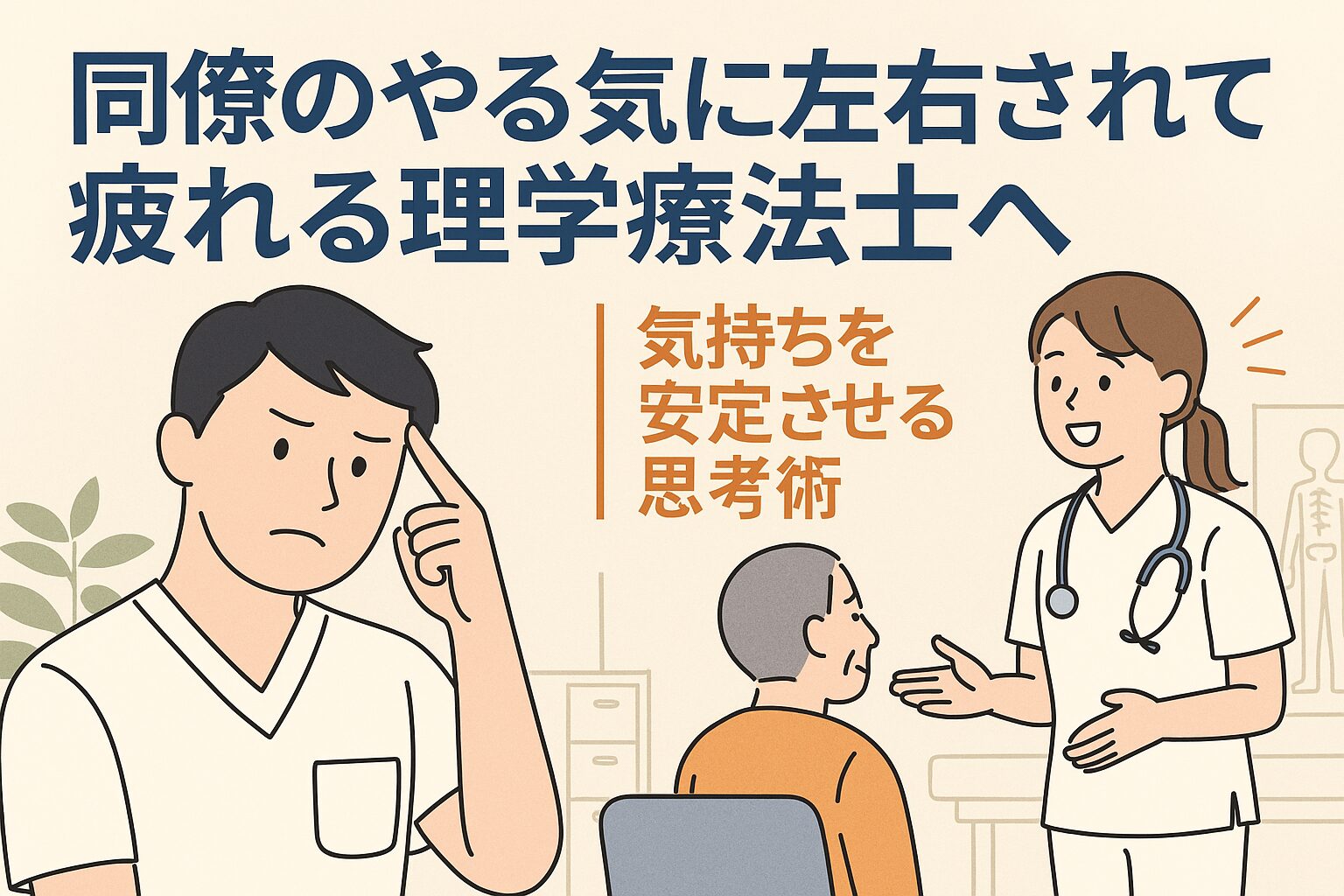


コメント