体幹の安定性は「深層筋の連携」から始まる
姿勢や動作の安定には、体幹の深層にある筋群が大きく関わります。とくに腹横筋と多裂筋は、腰椎や骨盤を支える「安定の要」。これらが十分に働かないと、
・腰痛が長引く/再発する
・歩行時にふらつく
・起き上がりや立ち上がりが不安定になる
といった問題が生じやすくなります。ここでは臨床で押さえたい評価と、協調的に使うための実践ポイントを解説します。
体幹筋群の2つのグループを理解する
① ローカル筋(深層安定化筋)
腹横筋・多裂筋・横隔膜・骨盤底筋など。関節や脊柱を微細に安定させ、姿勢保持の土台を担います。
② グローバル筋(表層筋)
腹直筋・外腹斜筋・脊柱起立筋など。大きな力発揮や運動を作ります。
理想はローカル筋で土台を作り、グローバル筋で動きを出すこと。深層筋が機能低下すると表層筋が代償し、姿勢の崩れや腰痛を招きやすくなります。
協調性を見る3つの評価視点
- タイミング:手足の動きに先行して、腹横筋・多裂筋が収縮しているか。
- 持続性(腹圧維持):動作中も呼吸を止めずに、お腹の張り(腹圧)を保てるか。
- 左右差・代償:回旋や立ち上がりで片側に偏らず、外腹斜筋・脊柱起立筋の過活動が出過ぎていないか。
臨床で使えるシンプルな評価法
① ドローイン(Draw-in)
軽くお腹をへこませて腹横筋を選択的に収縮。呼吸を止めずに腹圧を維持できるかを観察します。
観察ポイント:下腹部の張り/腰の過伸展がない/呼吸の自然さ。
② 多裂筋の触診
腹臥位でL4–L5付近の脊柱両側を軽く触診。上肢・下肢の小さな動きに伴う深部の膨らみ(収縮)とタイミング、左右差を確認します。
③ Bird-dog(四つ這い対角リーチ)
四つ這いで対角の手足を同時挙上。骨盤・体幹の動揺が小さく、腹圧が保てているかを評価します。動揺が大きければ深層筋の協調不良を示唆します。
臨床事例:体幹の協調性を高め歩行が安定したケース
症例:70代女性。腰痛と「歩くとふらつく」を主訴に来院。
評価:ドローインで腹圧維持が不十分/Bird-dogで骨盤動揺が大きい/多裂筋の収縮遅延あり。
介入:①仰臥位でのドローイン(呼吸と腹圧の連動)→ ②対側上肢挙上で多裂筋事前収縮の再教育 → ③Bird-dogで動作中の安定化練習。
結果:約4週間で腰痛が軽減し、歩行時の安定性が向上。患者も「歩いても疲れにくい」と自覚的改善を報告。
治療に生かすポイント
- 呼吸×腹圧の統合:横隔膜と腹横筋の同期を意識し、息を止めずに腹圧を高める。
- 多裂筋の“事前収縮”:小さな動き(上肢挙上など)で背腰部の先行安定を引き出す。
- 深層→表層の順序:ローカル筋で土台を作ってからグローバル筋で動作を統合する。
- ADL・歩行へ展開:立ち上がり・方向転換・階段などで「お腹を意識」を合言葉に再教育。
まとめ
腹横筋・多裂筋は「力の強さ」よりもタイミング・持続性・左右差を見極めることが重要。
呼吸・姿勢・動作を統合して使えるようにすることで、体幹制御の質が上がり、動作の安定・腰痛予防・歩行能力の向上につながります。


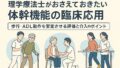
コメント